マンションの共有持分の買取交渉を有利に進め、適正価格で買い取ってもらう方法と手順
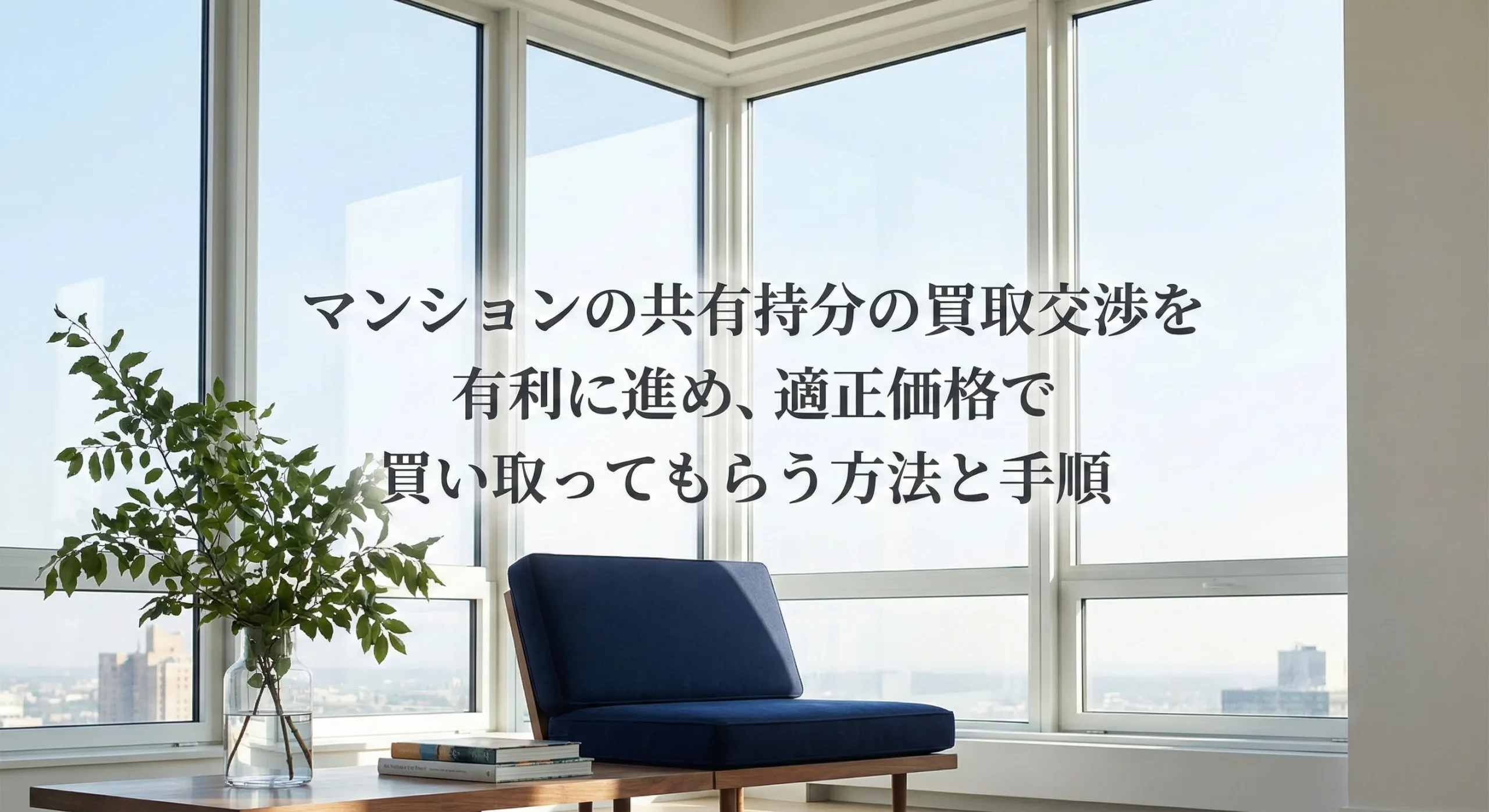
「相続で取得したマンションの共有持分を現金化したいのに、他の共有者が買い取ってくれない」
「提示された買取価格が不当に低い気がする…」
といった悩みを抱えていませんか?
住んでもいないマンションの共有持分を思いがけず相続することがありますが、住んでいる共有者の反対で売却もできず、固定資産税や管理費等の負担だけが続く「負動産」となりがちです。
共有関係を解消したくても、他の共有者との関係性や感情的なしがらみから、交渉が難航することも少なくありません。
この記事では、マンションの共有持分を適正価格で他の共有者に買い取ってもらうための交渉術、そして交渉がうまくいかなかった場合の最終手段である「共有物分割請求訴訟」について、相続に特化した弁護士が詳しく解説します。
マンションの共有持分の買取交渉でお悩みの方が、ご自身の法的な権利や交渉のやり方を理解し、納得のいく解決への一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。
共有とは?マンションが共有になる原因と共有の仕組み
まず、マンションの共有持分に関する交渉や手続きを理解する上で、基本となる「共有」と「持分」の法的な意味合い、そして共有者としての権利と義務について正確に把握しておくことが重要です。
共有とは?
「共有(きょうゆう)」とは、一つの物を複数の人が共同で所有している状態をいいます。
そして、それぞれの共有者がその物に対して持っている所有権の割合を「持分(もちぶん)」といいます。
例えば、マンションの一室をきょうだい3人で均等に相続した場合、各自が3分の1ずつの持分を持つことになります。
法律では、共有に関して、以下のようなルールが定められています。
- 共有物の使用(民法249条)
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます。
マンションの場合、持分が半分だからといって部屋の半分しか使えないわけではなく、原則として部屋全体を使用する権利があります。
ただし、複数の共有者がどのように「持分に応じて」使用するかは、共有者間の協議で決める必要があり、これが紛争の原因となることも少なくありません。
例えば、共有者の一人が無償で居住している場合、他の共有者は自身の持分に応じた賃料相当額の支払いを請求できる可能性があります。 - 共有物の変更(民法251条)
共有物に変更を加える行為(大規模なリフォーム、マンション全体の売却など)は、他の共有者全員の同意がなければ行うことができません。共有者の一人でも反対すれば、変更行為はできないため、共有不動産の活用や処分が非常に難しくなる一因です。 - 共有物の管理(民法252条)
共有物の管理に関する事項(賃貸借契約の締結・解除など)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決定します。
ただし、共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わない「軽微な変更」については、持分割合の過半数で決定できるよう、2023年4月施行の改正民法で要件が緩和されました。 - 共有物の保存(民法252条5項)
共有物の現状を維持するための「保存行為」(雨漏りの修理など)は、各共有者が単独で行うことができます。
このように、共有物の使用や管理、変更には他の共有者の同意が必要となる場面が多く、意思決定がスムーズにいかない場合、共有状態そのものが大きな制約となります。
マンションが共有になる主な原因
マンションが共有になる主な原因としては、以下のケースが挙げられます。
- 相続(遺産分割、遺言)
遺言によって複数の相続人に共同で相続させたり、被相続人が所有していたのが持分だったりするのが最も一般的なケースです。
もっとも、賃貸物件であれば、相続人間で賃料を分配するため、あえて共有のままにしておくこともあります。 - 生前贈与
親が子や孫にマンションの持分を生前贈与し、共有状態が生じることもあります。 - 夫婦や親子での共同購入
夫婦や親子が住宅ローンを共同で組むなどして資金を出し合い、マンションを購入した場合も共有となります(ただし、今回の記事の主眼である「相続等で意図せず共有になった」ケースとは少し異なります)。
特に相続によって共有関係になった場合、共有者同士が疎遠であったり、マンションに対する考え方(住みたい、売りたい、貸したいなど)が異なったりすることも多く、問題が顕在化しやすい傾向にあります。
共有者としての権利と義務
共有者であるあなたは、以下のような権利と義務を持っています。
【権利】
- 共有物の使用権
前述の通り、持分に応じて共有物全体を使用する権利があります(民法249条1項)。 - 共有物分割請求権
原則として、いつでも共有物の分割を請求することができます(民法256条1項本文)。
共有物分割請求権は、共有関係を解消するための非常に重要な権利であり、後で詳しく解説します。 - 自己の持分の処分権
各共有者は、他の共有者の同意なしに、自己の持分だけを自由に売却したり、担保に入れたりすることができます。
しかし、現実的には「持分のみ」を購入したいという第三者は稀であり、売却価格も低くなる傾向があります。
【義務】
- 管理費等の負担義務
各共有者は、その持分に応じて、管理費、修繕積立金、固定資産税・都市計画税などの共有物の負担を分担する義務があります(民法253条)。
たとえそのマンションに居住していなくても、あるいは全く使用収益を得ていなくても、共有持分を持っている限り、これらの費用負担義務からは逃れられません。この継続的な金銭的負担が、共有持分を現金化したいと考える大きな動機の一つとなることが少なくありません。
共有状態は、権利と同時に義務も伴います。
特に、利用していないにも関わらず費用負担だけが続く状況は、共有関係の解消、すなわち共有持分の売却や共有物分割を検討する強い理由となります。
【重要】共有持分の「適正価格」を把握する
共有持分の買取交渉において、最も重要かつ紛争になりやすいのが価格の問題です。
他の共有者にあなたの共有持分を買い取ってもらうためには、まずその共有持分の「適正価格」を客観的な根拠に基づいて把握し、提示する必要があります。
なぜマンションの評価額が重要なのか
共有持分の価値は、基本的に「マンション全体の評価額 × 持分割合」で計算されます。
したがって、交渉の出発点として、マンション全体の価値をいくらと見積もるかが極めて重要になります。
ここで評価額の認識が共有者間で大きく異なると、交渉は平行線をたどることになります。
なお、相続に関連して共有状態になった場合、「相続税申告時の評価額」を基準に考える共有者がいるかもしれません。
しかし、相続税評価額は、あくまでも税計算上の評価額にすぎず、特にマンションの場合、「適正価格」よりも低いことがほとんどである点に注意が必要です。
相続税評価額と市場価格(時価)の違い
マンションの評価額には、主に「相続税評価額」と「市場価格(時価)」の二つがあります。
しかし、これらは目的も算出方法も異なります。
相続税評価額
- 目的
相続税や贈与税を計算するために用いられる評価額です。 - 算出方法
国税庁が定める財産評価基本通達に基づいて計算されます。
多くの場合、土地は路線価方式または倍率方式、建物は固定資産税評価額を基にしており、一般的に市場価格よりも低くなる傾向があります。 - 注意点:
あくまで税計算上の評価額であり、実際の売買取引価格(時価)よりも低くなることが通常です。
特に、後述するタワーマンションなどの高層マンションでは、時価との乖離が大きくなる傾向があります。
市場価格(時価)
- 目的
実際に不動産市場で売買される際に、買い手と売り手の間で合意されるであろう価格を指します。
共有持分の買取交渉や、共有物分割訴訟における代償金の算定などでは、この市場価格(時価)を基準に考えるのが原則です。 - 算出方法
周辺の類似物件の取引事例、収益性、立地条件、建物の状態、需給バランスなど、様々な要因を総合的に考慮して評価されます。
相続税の申告で使った評価額が手元にあると、ついその金額を基準に考えがちです。
しかし、共有持分の買取交渉の場面では、あくまで「現在の市場で売ったらいくらになるか」という市場価格(時価)が基準になりなすので、時価を把握することが適正価格での売却を実現するためのポイントとなります。
国税庁も、タワーマンションの相続税評価額が市場価格と著しく乖離することを問題視し、2024年1月1日以降の相続・贈与から適用される新しい評価ルール(通称:タワマン節税防止ルール)を導入しました。
これは、市場価格との乖離が大きくなりやすい要因(築年数、総階数、所在階、敷地持分など)を評価額に反映させるもので、従来の評価方法よりも市場価格に近づけることを意図しています。
しかし、この改正をもってしても、相続税評価額はあくまで税務上の評価額であり、個別の物件の特性や最新の市場動向を完全に反映した「時価」そのものではありません。
したがって、共有持分の買取交渉においては、依然として市場価格を調査し、それを根拠とすることの重要性は変わりません。
この国税庁の動き自体が、従来の相続税評価額が市場の実態と著しく乖離していたこと、そして時価を重視する必要があることの裏付けとも言えます。
タワーマンションの共有持分の買取交渉をする際のポイント
タワーマンションや高層マンションは、一般的なマンションと比較して、相続税評価額と市場価格の乖離が特に大きくなりやすい傾向がありました。
その理由は、眺望、階数、共用施設の充実度、ブランドイメージといった要素が市場価格には強く反映される一方で、従来の画一的な相続税評価(特に固定資産税評価額を基にする部分)では十分に評価されにくかったためです。
前述の国税庁による評価ルールの改正は、まさにこの問題を是正しようとするものです。
新しいルールでは、評価額が市場価格予測値の60%未満となる場合に補正が行われるなど、より実態に近い評価を目指しています。
しかし、それでもなお、個別のプレミアム要素(例:角部屋、特別な眺望、内装のグレードなど)が完全に反映されるとは限らず、また市場の変動も早いため、タワーマンションの持分買取交渉においては、相続税評価額ではなく、最新の市場価格を把握することが特に重要です。
適正な市場価格(時価)を調べる方法
では、マンションの適正な市場価格(時価)はどのように調べればよいのでしょうか。
主な方法としては、以下の3つが挙げられます。
① 不動産取引価格情報(レインズ、公示価格など)の活用
- 概要
国土交通省が提供する「不動産取引価格情報検索」や、不動産流通機構が運営する「レインズ・マーケット・インフォメーション」などで、周辺の類似物件の成約価格を調べることができます。
公示価格や基準地標準価格も参考にはなりますが、これらは特定の地点の価格であり、マンション個別の評価には取引事例の方が有用です。 - メリット
比較的客観的な市場データに基づいており、無料で情報を得られます。 - デメリット
全く同じ条件の物件を見つけるのは難しく、情報の鮮度にも注意が必要です。
レインズの詳細データは宅建業者しかアクセスできませんが、不動産会社に依頼すれば類似物件の成約事例を出してもらうことが可能です。 - 活用法
まずはこれらの公的データや簡易査定サイトで相場観を掴むのが良いでしょう。
② 不動産鑑定士による査定
- 概要
国家資格を持つ不動産鑑定士に依頼し、詳細な調査に基づいて「不動産鑑定評価書」を作成してもらいます。 - メリット
非常に信頼性が高く、客観的な評価額の証明となります。
裁判になった場合にも有力な証拠となります。 - デメリット
数十万円程度の費用がかかり、評価書の作成にも時間がかかります。 - 活用法
交渉が難航しそうな場合や、訴訟も視野に入れる場合には、鑑定評価の取得を検討する価値があります。
鑑定評価書は、価格交渉において強力な武器となり得ます。
③ 不動産会社による簡易査定
- 概要
地域の不動産会社に依頼して、無料で査定(簡易査定、机上査定)をしてもらいます。
多くの場合、前述のレインズデータや自社の取引実績、市場動向を基に算出されます。 - メリット
手軽で費用がかからず、スピーディーに概算価格を知ることができます。
複数の会社に依頼することで、より客観的な価格帯が見えてきます。 - デメリット
あくまで簡易的な評価であり、会社によっては、売却を促すために高めの査定額を出してくる可能性もあります。
また、不動産鑑定評価書ほどの法的証明力はありません。 - 活用法
まず相場を知るための第一歩として有効です。
複数の査定結果を比較検討しましょう。
これらの方法を組み合わせ、できるだけ客観的で説得力のある市場価格(時価)を把握することが、次の交渉ステップに進むための重要な準備となります。
マンションの共有持分を高値で買い取ってもらうための戦略
適正な市場価格(時価)を把握したら、いよいよ他の共有者との買取交渉に臨みます。
感情的にならず、冷静かつ戦略的に進めることが、納得のいく価格での合意形成につながります。
交渉前の準備:証拠固めが肝心
交渉を始める前に、以下の準備をしっかりと行いましょう。
- 客観的な評価額資料の収集
市場価格(時価)の根拠資料(類似物件の取引事例、不動産会社の査定書、可能であれば不動産鑑定評価書など)を収集します。
複数の資料があれば、より説得力が増します。 - 希望買取価格の明確化
収集した根拠資料に基づき、マンション全体の時価を検討し、そこから自身の持分割合に応じた具体的な希望買取価格を計算します。 - 交渉相手の状況分析(可能であれば)
相手がどのような状況にあるか(資金力、マンションへの思い入れ、他の共有者との関係など)を可能な範囲で把握しておくと、交渉の進め方を考える上で役立ちます。 - 想定される反論への準備
相手からどのような反論(価格が高い、お金がない、売りたくない等)が出てくるかを予測し、それに対する回答や代替案をあらかじめ考えておきます。
準備不足のまま交渉に臨むと、相手のペースに巻き込まれたり、感情的な言い争いになったりしがちです。
客観的な証拠に基づいた冷静な主張こそが、交渉を有利に進めるための鍵となります。
交渉の進め方:冷静かつ論理的に
準備が整ったら、以下の点に留意して交渉を進めましょう。
- 丁寧なアプローチ
まずは、共有持分を買い取ってほしい旨とその理由(例:現金化の必要性、管理負担の軽減など)を丁寧に伝えます。
電話だけでなく、後々の記録のためにも書面(手紙やメール)で申し入れることも有効です。 - 希望価格と根拠の提示
把握した市場価格(時価)に基づいた希望買取価格を具体的に提示し、その算出根拠となった資料(査定書や取引事例など)を示します。
相手が相続税評価額を主張してくる可能性もありますので、なぜ市場価格(時価)が基準となるのかを説明できるようにしておきましょう。 - 相手の意見の傾聴
相手の言い分や状況にも耳を傾ける姿勢が大切です。
一方的に要求を突きつけるのではなく、対話を通じて合意点を探る努力をしましょう。 - 冷静さの維持
交渉が難航しても、感情的になったり、相手を非難したりするのは避けるべきです。
あくまで目標は「共有持分の適正価格での買取り」であり、論理的な主張を続けることが重要です。
よくある反論と対応策
交渉では、以下のような反論が出ることが想定されます。
- 反論①:提示された価格が高すぎる
(対応策)
提示した価格が市場価格(時価)に基づいていることを、収集した資料(取引事例、査定書等)を再度示して丁寧に説明します。 - 相手が相続税評価額や古い情報、比較対象として不適切な事例を持ち出してきた場合は、なぜそれが今回の買取価格の基準として妥当でないのかを具体的に指摘します。
価格の妥当性についてどうしても意見が合わない場合は、「中立的な不動産鑑定士に共同で鑑定を依頼しませんか?」と提案することも有効な場合があります。 - 反論②:共有持分を買い取る資金がない
(対応策)
まずは相手の状況に理解を示しつつ、分割払い(ただし、支払い保証などリスク対策が必要)や、金融機関からのローン調達といった選択肢を検討するよう促します。
そして、「もし、どうしても当事者間での解決が難しい場合は、法的な手続き(共有物分割請求)に進む可能性も考えなければなりませんが、そうなるとお互いにとって望まない結果(例:競売による低価格売却)になる可能性もあります」と、次のステップを示唆することで、相手に資金調達の必要性を認識させることも考えられます。 - 反論③:今の共有状態を維持したい
(対応策)
相手が現状維持を望む気持ちは尊重しつつも、「共有状態を続けることが双方にとって負担になっている現状」と「持分を現金化したいという正当な要求」を改めて伝えます。
そして、「共有関係は、本来、共有者間の協力があって成り立つものですが、それが難しい以上、法律は共有関係を解消する手段(共有物分割請求)を認めています」と、法的な権利があることを冷静に伝えます。これは脅しではなく、交渉が決裂した場合の次の選択肢を事実として伝えるという姿勢が重要です。
第三者への売却の可能性と難しさ
交渉相手である他の共有者がどうしても買い取ってくれない場合、「自分の共有持分だけを第三者に売却できないか?」と考えるかもしれません。
法律上は、各共有者は他の共有者の同意なしに、自己の共有持分のみを第三者に売却することが可能です。
しかし、現実的には、多くの困難が伴います。
- 買い手の限定
マンションの「共有持分のみ」を購入したいという一般の買い手は非常に稀です。
購入しても単独で物件全体を自由に使用・処分できるわけではなく、他の共有者との間で将来的なトラブルに巻き込まれるリスクもあるためです。 - 専門買取業者の買取価格の低さ
共有持分を専門に買い取る不動産業者も存在しますが、彼らは買い取った共有持分を元に他の共有者と交渉したり、最終的に共有物分割請求訴訟を起こしたりして利益を得ることを目的としています。
そのため、買取価格は、市場価格から算出した持分相当額よりも大幅に低くなるのが一般的です。
上記の理由から、共有持分のみを第三者に売却する場合、その価格は、時価よりもかなりディスカウントされた金額(場合によっては半額以下)になることを覚悟しなければなりません。
もっとも、共有持分のみを第三者に売却できるという事実は、他の共有者との交渉において、間接的なプレッシャーとして機能する場合があります。
「このまま交渉が決裂すれば、私はやむを得ず第三者(専門業者など)に共有持分を売却することも考えなければなりませんが、そうなると見知らぬ業者が新たな共有者として入ってくることになり、あなたにとっても好ましい状況ではないでしょう。それよりは、我々の間で適正な価格で解決する方がお互いにとって良いのではないでしょうか?」といった形で、相手にとっても共有者間での解決が望ましい選択肢であることを示唆することができます。
これは、次に紹介する共有物分割請求訴訟と合わせて、交渉を有利に進めるための材料になります。
交渉が決裂したら?最終手段としての「共有物分割請求訴訟」
交渉での共有持分の買取りが進まない場合、法律は、共有関係を解消するための最終手段として、「共有物分割請求訴訟」という手続きを認めています。
この制度を理解しておくことは、交渉を有利に進めるためにも、また、いざという時の備えとしても重要です。
共有物分割請求権とは?
民法第256条1項本文には、「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」と定められています。
重要なのは、これが「請求権」であるということです。
つまり、あなたが分割を望めば、他の共有者は原則としてこれを拒否することはできません。
共有者間で分割方法について協議が調わない場合、裁判所に訴訟を提起し、裁判所の判断によって分割方法を決めてもらうことができます。
これが共有物分割請求訴訟です。
共有物分割請求訴訟の流れ
共有物分割請求訴訟は、一般的に以下のような流れで進みます。
- 訴訟提起:
共有マンションの所在地を管轄する地方裁判所(または簡易裁判所、請求額による)に訴状を提出します。 - 答弁書提出
訴えられた他の共有者(被告)は、訴状に対する反論や自身の希望する分割方法などを記載した答弁書を提出します。 - 争点整理
裁判所は、原告・被告双方の主張を聞き、何が争点となっているのか(例:物件の評価額、分割方法の希望など)を明確にします。
書面での主張・反論のやり取り(準備書面)や、弁論準備手続期日(非公開の協議)が行われることが多いです。 - 証拠調べ(鑑定評価など)
物件の評価額について争いがある場合、裁判所が選任した不動産鑑定士による鑑定評価が行われることが一般的です。
鑑定費用は、原則として当事者が持分割合に応じて負担します。 - 当事者尋問
論点によっては、原告や被告本人に対する尋問が行われることもあります(権利濫用の抗弁の場合など)。 - 和解の試み
多くの共有物分割訴訟は、判決に至る前に和解によって終了します。
特に、相手が住んでいる共有マンションであれば、裁判所は、訴訟上の和解を勧めるのが一般的です。 - 判決
和解が成立しない場合、裁判所が最終的な判断として、具体的な分割方法を命じる判決を下します。
裁判所が命じる3つの分割方法
共有物分割訴訟において、裁判所は、以下のいずれかの方法、またはこれらを組み合わせた方法で分割を命じます。
① 現物分割
- 内容
共有物を物理的に分割する方法です。
典型的なのは、広大な土地を複数の区画に分筆するようなケースです。 - マンションへの適用
一戸のマンションを物理的に分割することは、現実的に不可能です。
したがって、共有物がマンションの一室である場合、現物分割が命じられることはまずありません。
② 代償分割
- 内容
共有者の一人が物件全体を取得する代わりに、他の共有者に対して、その共有持分の価格に相当する金銭(代償金)を支払う方法です。 - 要件
物件を取得する共有者に十分な支払い能力があること、そして、この方法が共有者間の公平を害さないと裁判所が判断することが必要です。 - マンションへの適用
共有者の一人がそのマンションを取得したいと強く希望し、かつ、他の共有者の共有持分を買い取るだけの資力がある場合には、この方法が採用される可能性があります。
裁判所は、当事者の意向や資力を考慮して、この方法が適切かを判断します。判例(最判平成8年10月31日)では、共有物の性質、共有者間の関係、利用状況などを総合的に考慮し、代償分割を含む適切な分割方法を選択できる柔軟性を認めています。これは、裁判所が実質的な「買取命令」に近い判断を下せることを意味します(要件を満たすことが前提ですが)。
③ 換価分割
- 内容
共有物を第三者に売却し、その売却代金から諸経費を差し引いた残額を、各共有者の持分割合に応じて分配する方法です。
売却は、原則として裁判所が主導する競売によって行われますが、当事者全員が合意すれば、市場での任意売却がなされることもあります。 - マンションへの適用
共有物がマンション一室のように物理的に分割できず(現物分割が不可)、かつ、共有者の誰もが代償金を支払って単独所有を希望しない(または資力がない)場合、 この換価分割が命じられる可能性が最も高くなります 。 - 注意点:
競売による売却価格は、一般的に市場価格よりもかなり低くなる(市場価格の5~7割程度とも言われる)傾向があります。
これは、共有者全員にとって経済的な損失につながる可能性があります。
マンションの共有物分割訴訟では、現物分割は不可能であり、代償分割も特定の条件が整わない限り難しいため、最終的に換価分割(特に競売)に至るケースが多いという現実があります。
この「競売による低価格での強制売却」という可能性こそが、交渉における強力なプレッシャーとなり得るのです。
表: 共有物分割の方法と特徴
| 分割方法 | 概要 | マンションへの適用 | 主な特徴・結果 |
|---|---|---|---|
| 現物分割 | 共有物を物理的に分ける | ほぼ不可能 | 土地の分筆などが典型。マンション一室には適用できない。 |
| 代償分割 | 一人が全体を取得し、他の共有者へ持分相当額の金銭(代償金)を支払う | 可能(要件あり) | 取得希望者と資力が必要。実質的な「買取」。裁判所が適切と判断すれば命じられる。 |
| 換価分割 | 共有物を売却し、代金を持分割合で分配する(主に競売) | 最も可能性が高い | 現物分割・代償分割が困難な場合の最終手段。競売価格は市場価格より大幅に低くなる傾向があり、全共有者にとって経済的損失のリスクがある。 |
訴訟にかかる期間と費用
共有物分割請求訴訟には、相応の時間と費用がかかります。
- 期間
事案の複雑さや当事者間の争いの程度にもよりますが、訴訟提起から判決(または和解成立)まで、1年~2年程度かかることもあります。 - 費用
- 弁護士費用
弁護士に依頼する場合、相談料、着手金、成功報酬などが発生します。
費用体系は事務所によって異なります。 - 裁判所費用
- 印紙代(収入印紙)
訴状に貼る印紙代で、訴訟の対象となる不動産の評価額(通常は固定資産税評価額)に応じて決まります。 - 予納郵券(郵便切手)
裁判所から当事者への書類送達などに使われる郵便切手代で、6000円程度を事前に納めます。 - 鑑定費用
裁判所が不動産鑑定を命じた場合、その費用(数十万円程度が一般的)は、原則として当事者が持分割合などに応じて負担することになります。
- 印紙代(収入印紙)
- 弁護士費用
これらの費用は、最終的に得られる(あるいは支払う)金額から差し引かれることを意味するため、訴訟になるまで揉めれば、当事者全員の手取り額が減少する可能性もあります。
このコスト面も、訴訟を避けて交渉で解決するインセンティブとなります。
共有物分割請求を交渉の切り札にする方法
ここまで見てきたように、共有物分割請求訴訟は、時間も費用もかかり、最終的に競売による低価格売却という望まない結果になるリスクも伴います。
しかし、この「最終手段」の存在と内容を理解し、交渉の場で適切に活用することで、他の共有者との買取交渉を有利に進めることが可能になります。
交渉のパワーバランスを変える
あなたが共有物分割請求権という法的な権利を持っていること、そして、必要であれば訴訟を提起する準備があることを相手に認識させるだけで、交渉の力関係は大きく変化します。
現状維持を望んでいたり、不当に安い価格での買取を提示してきたりする共有者にとって、「いつでも分割請求され、最終的には裁判所の判断で強制的に共有関係が解消されてしまう可能性がある」という事実は、大きなプレッシャーとなります。
法律で認められている共有物分割請求権は強力であり、相手が単に「分割には応じない」と拒否し続けることはできないからです。
これにより、「分割するかどうか」ではなく、「どのように分割するか」の問題に移ります。
相手に「訴訟のデメリット」を理解させる
交渉の場で、共有物分割請求訴訟に至った場合の相手方にとってのデメリットを、感情的にならず、客観的な事実として伝えることが有効です。
- 強制的な売却リスク(換価分割のリスク)
「もし話し合いで解決できなければ、裁判所に分割を求めることになります。マンションの場合、最終的に裁判所が物件全体の売却(換価分割)を命じる可能性が高いです。特に競売となると、市場価格よりもかなり安い価格で売却されてしまうことが多く、お互いにとって損になります。」と伝え、相手が望む「物件の維持」ができなくなるリスクと、経済的な損失リスクを具体的に示します。 - 時間と費用
「裁判になると、解決までに1年~2年かかることもありますし、弁護士費用や鑑定費用など、少なくない費用がお互いにかかってきます。その分、最終的に手元に残るお金も減ってしまいます。」と、訴訟の現実的な負担を説明します。 - 精神的負担と関係悪化
「裁判という手続きは、精神的にも大きな負担になりますし、残念ながら親族間の関係もさらに悪化してしまう可能性があります。」と、金銭面以外のデメリットにも触れます。 - コントロールの喪失
「裁判所の判断に委ねるということは、私たち自身で解決方法を決めるコントロールを失うということです。話し合いであれば、お互いが納得できる条件を探る余地がありますが、判決となればそれに従うしかありません。」と、交渉による解決のメリットを対比させます。
これらのデメリットを伝える目的は、相手を脅すことではありません。
あくまで、「交渉が決裂した場合に、法的な手続きに移行すると、このような現実が待っている」ということを冷静に理解してもらい、「それならば、今の段階で、お互いにとってより良い条件(=適正な市場価格での買取)で合意する方が合理的ではないか」と考えさせることにあります。
建設的な最終提案として位置づける
共有物分割請求の可能性に言及する際は、それを「脅し」ではなく、「交渉が不調に終わった場合の、法に定められた次のステップ」として、建設的な最終提案の文脈で提示することが重要です。
例えば、以下のような伝え方が考えられます。
「この不動産鑑定評価書(または査定書)が示すように、このマンションの現在の市場価値は約〇〇万円と考えられます。私の持分(〇分の〇)相当額である〇〇万円で買い取っていただけるのが、お互いにとって最も公平で現実的な解決策だと考えています。もちろん、すぐに全額が難しいようでしたら、支払い方法については相談に応じる用意があります。
ただ、もしこの価格での合意がどうしても難しいということであれば、残念ですが、共有関係を解消するための法的な手続きである共有物分割請求訴訟を検討せざるを得なくなります。先ほどお話ししたように、訴訟となると時間も費用もかかりますし、最終的に競売で安く売却されてしまう可能性も否定できません。そうなってしまう前に、なんとか私たち自身で、この適正な価格に基づいて円満に解決できればと強く願っています。もう一度、この価格での買取をご検討いただけないでしょうか。」
このように、相手への配慮を示しつつも、分割請求という選択肢があることを明確に伝え、それと比較して「今、ここで適正価格で合意すること」が双方にとってメリットのある選択肢であることを論理的に示すことが、交渉を妥結に導くための鍵となります。
目指すべきは、訴訟を起こすことではなく、訴訟の可能性とその結果を背景に、相手に「適正価格での買取に応じる方が得策だ」と判断してもらうことなのです。
まとめ
相続や生前贈与によって共有となったマンションの共有持分を買い取ってもらいたいと考えたとき、他の共有者との交渉は一筋縄ではいかないことも少なくありません。
しかし、正しい知識と戦略を持って臨めば、道は開けます。
本記事では、以下の重要なポイントを解説しました。
- 共有の基本
共有とは何か、共有者としての権利(使用権、分割請求権など)と義務(費用負担など)を理解すること。 - 適正価格の把握
交渉の鍵は「市場価格(時価)」であり、相続税評価額とは異なること。
特にタワーマンションでは注意が必要なこと。
そして、取引事例、鑑定評価、不動産会社査定など、時価を調べる具体的な方法。 - 有利な交渉戦略
事前の証拠固め、冷静かつ論理的な交渉の進め方、よくある反論への対応策、そして第三者への持分売却の現実的な難しさ。 - 最終手段としての「共有物分割請求訴訟」
交渉が決裂した場合の法的手段であり、その権利(民法第256条)、手続きの流れ、裁判所が命じる分割方法(特にマンションでは換価分割=競売のリスクが高いこと)、そして訴訟に伴う時間と費用。 - 訴訟を交渉の切り札に
共有物分割請求の可能性とそれがもたらすデメリット(強制売却、コスト、時間、精神的負担)を相手に理解させることが、適正価格での買取合意への強力な後押しとなること。
共有不動産の持分に関する問題は複雑に感じられるかもしれませんが、一つ一つのステップを理解し、ご自身の状況に合わせて準備を進めれば、必ず道は開けます。
本記事で解説したポイントが、皆様が抱える共有持分の問題を解決し、希望する結果(=有利な条件での現金化)を実現するための一助となることを願っております。

