自筆の遺言書は「検認」が必要!家庭裁判所の手続きの流れや必要書類を解説
自筆(手書き)の遺言書を相続手続きで使うためには、家庭裁判所で「検認の手続き」をする必要があります。特に初めての相続ですと、遺言書を発見した後、どうしたらいいか分からない相続人もおられるかもしれません。しかし、裁判所の手続きとはいえ、ポイントさえ分かっていれば、誰にでもできる簡単な手続きです。相続に特化した弁護士が「検認の手続き」の流れや必要書類を解説します。
「遺言書の検認」とは?検認が必要な場合と不要な場合
被相続人(亡くなった人)が自筆(手書き)で書いた遺言書(自筆証書遺言)を発見したら、すみやかに「遺言書の検認」という手続きが行う必要があります(民法1004条1項)。
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
どういう手続きか一言で言いますと、自筆の遺言書を家庭裁判所に持参し、開封及び状態を確認してもらう手続きになります。
つまり、遺言書の検認は、家庭裁判所が遺言の方式を調査し、遺言書の状態を確定するための手続きです。
後日の紛争に備えて偽造・変造を防止し、遺言書の原状を保全するが目的ですので、家庭裁判所が遺言書の有効性を確認するための手続きではありません。
とはいえ、自筆の遺言書で預金の解約や相続不動産の名義変更などを行うためには、家庭裁判所で検認済証明書をつけてもらう必要があります。
相続手続きを進めるため、いずれにせよ遺言書の検認が必要です。
これに対し、公正証書遺言は、遺言書の検認が不要です(民法1004条2項)。
遺言書の原本が公証役場に保管されますので、偽造・変造や紛失・隠匿等のおそれがないからです。
そのため、検認をせず、相続手続きをスムーズに進めようと思った場合、従来は、公正証書遺言を作成する必要がありました。
しかし、自筆の遺言書であっても、「自筆証書遺言の保管制度」により法務局で保管されている遺言書は、検認が不要になりました。
公正証書と同様、偽造・変造や紛失・隠匿等のおそれがないからです。
2020年7月10日からスタートした新しい制度ですが、今後は利用が増えていくものと思われます。
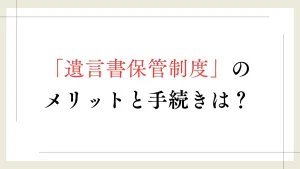
検認せずに遺言書を開封するとどうなる?
自筆の遺言書は、封筒に入れて封をし、表に「遺言書」と記載されている場合が多いです。
遺言書を見つけると、内容が気になり、封を開けたくなるかもしれません。
しかし、封がしてある遺言書は、法律上、家庭裁判所の検認手続きにおいて開封する必要があります(民法1005条)。
もし検認せずに遺言書を開封してしまった場合、開封者は、5万円以下の過料に科されます。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
過料というのは、行政上の秩序の維持のために、違反者に制裁として金銭的負担を課すものです。
刑事事件における罰金とは異なり、過料に科せられても前科にはなりません。
実際のところ、過料の制裁が発動されることはほぼありません。
しかし、法律上は禁止されていますし、他の相続人から偽造したと疑われることもあります。
封がしてある遺言書を見つけたら、そのまま開封してしまわないよう注意してください。
万が一、検認の手続きについて知らず、遺言書を開封してしまったとしても、それで遺言書が無効になるわけではありません。
封筒を含めて捨ててしまわず、すみやかに遺言書の検認を申し立ててください。
遺言書の検認はどのように申し立てる?(申立人・必要書類など)
遺言書の検認は、家庭裁判所に申し立てます。
以下、検認を申し立てる際に知っておくべきことについて、具体的に解説します。
申立人
まず、遺言書の検認を申し立てるのは、以下の人たちです。
・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人
実務上は、相続人が遺言書を発見し、そのまま検認を申し立てることが多いです。
管轄裁判所
検認を申し立てるのは、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
遺言者が東京23区ないし島しょ部に居住していたのであれば、管轄裁判所は東京家庭裁判所です。
東京都のそれ以外の地域に居住していたのであれば、管轄裁判所は東京家庭裁判所立川支部です。
申立てに必要な費用・書類
・収入印紙:800円(遺言書1通につき)
・郵便切手:各管轄裁判所に確認
東京家庭裁判所の場合(2023年12月時点)
84円×(申立人+相続人の数×2)
10円×(申立人+相続人の数)
・必要書類:
①遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
②相続人全員の戸籍謄本
③(代襲相続人・次順位相続人)代襲相続人・次順位相続人であることが分かる戸籍謄本
*遺言書自体は、検認期日の当日、家庭裁判所に持参します。
検認の手続きの流れ
①遺言書の検認の申立て
検認の申立書、収入印紙、郵便切手、必要書類を揃え、管轄裁判所に検認の申立てをします。
検認の申立書は、裁判所のホームページで書式がダウンロードできます。
記入例もありますので、それを見れば誰でも作成できます。
②検認期日の日程調整
申立後、裁判所から検認を行う日(検認期日)の日程調整の連絡が来ますので、2週間~1か月後くらいを目安に検認期日を決めます。
③検認期日通知書の送付
申立人と相続人に対し、検認期日通知書(案内状のようなもの)が送付されます。
④検認期日への出席
申立人は、遺言書の原本、申立書に押した印鑑、身分証明書等を持参し、検認期日に出席します。
申立人以外の相続人の出席は任意ですので、出席しなくても検認期日は行われます。
⑤検認の実施
出席した相続人などの立会いのもと、遺言書を開封し、遺言書の状態、筆跡、押印などを確認します。
裁判官から、筆跡や押印が遺言者のものか、遺言書の発見場所、保管場所、保管方法などを聞かれますので、分かる範囲で答えてください。時間は10~15分程度です(通常は)。
⑥遺言書検認済証明書の交付
「遺言書検認済証明書」の交付を請求すると、裁判所書記官が遺言書と証明書を合綴し、申立人に渡してくれます。

