遺留分の請求は自分でできる?弁護士に依頼すべきケースとメリット・デメリット
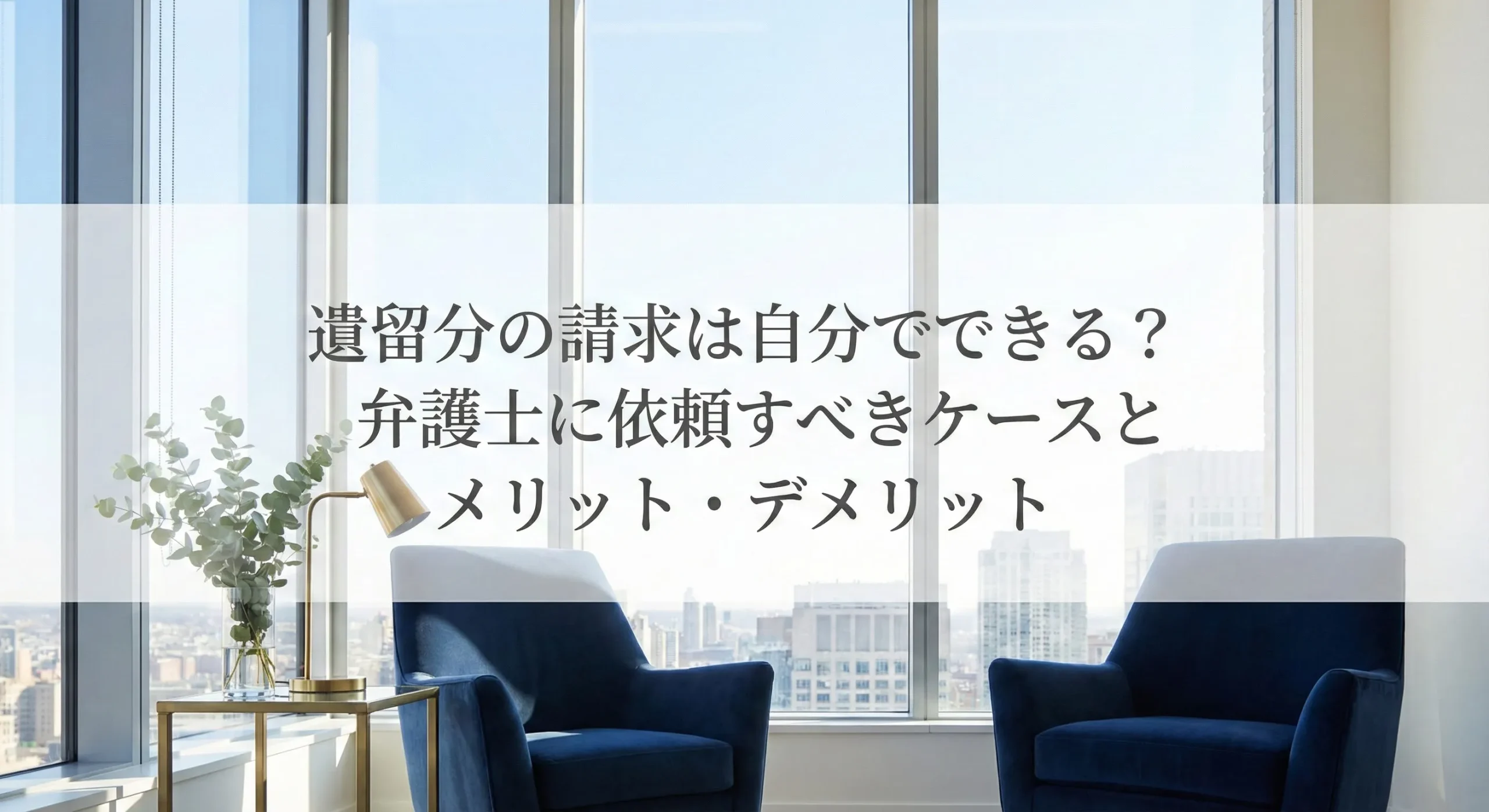
「父の遺言書を見たら、兄に全財産を譲ると書かれていて、自分には全く相続分がなかった…」
「遺言書の内容は不公平だと感じるけれど、遺言書がある以上、従うしかないのだろうか…」
このような状況に置かれたとき、大きなショックとともに、強い不満を感じるかもしれません。
特に、普通にご両親と交流してきたと思っていた方にとっては、納得が行かないのは当然のことです。
しかし、諦める必要はありません。
相続人には、遺言書の内容にかかわらず、最低限の遺産を受け取る権利が保障されています。
これを「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。
遺留分が侵害されている場合、その侵害額に相当する金銭を請求することができます。
ただ、遺留分の請求について、「費用を抑えたいから、できれば自分で手続きを進めたい」「弁護士に頼むべきか迷っている」とお考えの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、遺留分の請求をご自身で行う場合の具体的な流れ、注意点、そして弁護士に依頼する場合のメリット・デメリットについて、相続に特化した弁護士が詳しく解説します。
この記事を読むことで、以下の点が明確になります。
- 遺留分とは何か、誰に権利があるのか
- 遺留分侵害額請求を自分で行う場合の具体的な手順と注意点
- 遺留分請求を「自分でできるか」の判断基準
- 弁護士に依頼せずに自分で手続きを進める場合のデメリット
- 弁護士に依頼するメリットと、依頼を検討すべき具体的なケース
ご自身の状況に合わせて、最適な方法を判断するための一助となれば幸いです。
法律で保障されている相続人の権利「遺留分」
まず、遺留分制度の基本的な内容について確認しましょう。
遺留分とは?
遺留分とは、相続人に法律上保障されている最低限の取り分のことです。
被相続人(亡くなった方)は、遺言により、自分の財産を誰にどのように相続させるかを自由に決めることができます。
しかし、その自由を無制限に認めると、例えば「愛人に全財産を譲る」といった遺言が作成された場合、残された家族の生活が成り立たなくなる可能性があります。
そこで、被相続人の財産処分の自由と相続人の生活保障や公平性の観点とのバランスを取るため、遺留分制度が設けられています。
これにより、遺言によっても奪うことのできない、相続人の最低限の権利を保障しているのです。
遺留分権利者(遺留分を有する相続人)
遺留分権利者(遺留分を有する相続人)は、以下の範囲に限られます。
- 配偶者
- 子(子が既に亡くなっている場合は孫などの代襲相続人)
- 直系尊属(親、親が亡くなっている場合は祖父母など。子がいない場合に相続人となる)
重要なポイントは、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないということです。
したがって、遺言で兄弟姉妹に相続分がないとされていても、遺留分を請求することはできません。
遺留分の割合
遺留分の全体(総体的遺留分)の割合は、相続人の構成によって異なります。
- 直系尊属のみが相続人の場合:相続財産の3分の1
- 上記以外(配偶者のみ、子のみ、配偶者と子、配偶者と直系尊属)の場合:相続財産の2分の1
個々の遺留分権利者が持つ具体的な遺留分(個別的遺留分)は、この総体的遺留分に、各自の法定相続分を掛けて計算します。
【例】相続人が配偶者と子2人の場合
- 総体的遺留分:相続財産の2分の1
- 配偶者の法定相続分:2分の1
- 子の法定相続分:2分の1 × 1/2 = 4分の1(各子)
したがって、それぞれの個別的遺留分は、
- 配偶者の遺留分:1/2 × 1/2 = 4分の1
- 子の遺留分:1/2 × 1/4 = 8分の1(各子)
となります。
遺留分侵害額請求権とは?(法改正による変更点)
以前は、遺留分を侵害された相続人は、遺贈や贈与された財産そのものの返還を求める権利(遺留分減殺請求権)を持っていました。
これにより、例えば不動産などが共有状態となり、その後の利用や処分が困難になるケースがありました。
しかし、2019年7月1日の民法改正により、遺留分制度は大きく変わりました。
現在は、遺留分を侵害された場合、侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利(遺留分侵害額請求権)へと変更されています。
つまり、原則として特定の財産(不動産など)そのものを取り戻すのではなく、「お金で解決する」という形になったのです。
これにより、財産の共有状態を避け、より円滑な解決が図られるようになりました。
民法 第1046条(遺留分侵害額の請求)
1. 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。(出典:e-Gov法令検索 民法)
遺留分の請求を自分でする場合の流れと注意点
では、遺留分の請求を自分でする場合、どのような手順を踏むのでしょうか。
以下、主な流れと特に注意すべき点について解説します。
ステップ1:遺留分侵害額の計算
まず、ご自身の遺留分が具体的にいくら侵害されているのかを計算する必要があります。
遺留分の請求をする際、最初に行う重要なステップです。
遺留分侵害額は、以下の計算式で求められます。
遺留分侵害額 = 遺留分額 - (遺留分権利者が相続で得た財産額 + 特別受益額)
ここで、「遺留分額」はさらに以下の計算で求めます。
遺留分額 = 遺留分算定の基礎となる財産の価額 × 個別的遺留分割合
この「遺留分算定の基礎となる財産の価額」を正確に把握することが、計算の最初の関門となります。
これは、単純な相続開始時の遺産総額ではありません。
以下の要素を考慮する必要があります。
- 相続開始時(亡くなった時点)のプラスの財産:預貯金、不動産、株式、自動車など
- 被相続人が負っていた債務:借金、未払金など(これはマイナス要素として差し引きます)
- 一定期間内の贈与:
- 相続人以外への贈与
原則として相続開始前1年以内のもの。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合は、1年以上前のものでも加算されます。 - 相続人への贈与(特別受益に該当するもの)
原則として相続開始前10年以内のもの。婚姻、養子縁組、生計の資本としての贈与などが該当します。
- 相続人以外への贈与
【計算の難しさ・注意点】
- 財産調査の網羅性
被相続人がどのような財産を持っていたか、すべてを正確に把握するのは困難な場合があります。
特に、生前の贈与については、記録が残っていないことも多く、調査が難航する可能性があります。 - 財産の評価
預貯金のように金額が明確なものばかりではありません。
不動産(土地・建物)、非上場株式、美術品などは、評価額を算定する必要があります。
評価方法によって金額が大きく変わるため、どの時点の、どの評価基準(固定資産税評価額、路線価、実勢価格など)を用いるかが問題となります。 - 特別受益の該当性
相続人への生前贈与が「特別受益」に該当するかどうか(遺産の前渡しと評価されるか)の判断は、法律的な知識を要する場合があります。 - 計算の複雑さ
上記の要素をすべて考慮して正確な遺留分侵害額を算出するのは、専門家でなければかなり難しい作業です。
計算ミスがあると、本来もらえるはずの金額より少なく請求してしまったり、逆に過大な請求をして紛争が泥沼化したりするリスクがあります。
ステップ2:遺留分請求の意思表示(内容証明郵便の活用)
遺留分侵害額を計算したら、次は遺留分を侵害している相手方(遺贈や贈与を受けた人)に対して、「遺留分侵害額を支払ってください」という意思表示をする必要があります。
この意思表示は、法律上、特定の方式は定められていません。
そのため、口頭で伝えることも可能です。
しかし、後で「言った」「言わない」の水掛け論になるのを避けるため、証拠が残る方法で行うことが極めて重要です。
そこで一般的に利用されるのが「内容証明郵便(配達証明付き)」です。
遺留分を請求する内容証明を自分で作成・送付することも可能です。
【内容証明郵便とは】
- いつ:郵便物の差出日付
- 誰から誰へ:差出人と受取人
- どのような内容の文書:文書の内容
を郵便局(日本郵便株式会社)が証明してくれるサービスです。
これに「配達証明」を付けることで、相手方に郵便物が配達された日付も証明できます。
【内容証明郵便で送る理由】
- 請求の証拠保全
遺留分侵害額請求権を行使した事実とその日付を明確に証明できます。
これは、後述する「時効」との関係で非常に重要です。 - 相手方への心理的効果
正式な書面で請求が届くことで、相手方も問題を真剣に受け止め、話し合いに応じやすくなる可能性があります。
【自分で内容証明郵便を作成・送付する際の注意点】
- 書式・字数制限
内容証明郵便には、1行あたりの文字数や1枚あたりの行数に制限があります(縦書き・横書きで異なります)。
句読点や括弧も1文字としてカウントされます。書式を守らないと受理されません。 - 記載内容の正確性
誰から誰への請求か(当事者の特定)、どの相続に関する遺留分請求か(被相続人の特定)、請求する意思などを明確に記載する必要があります。
請求金額は、最初の段階で確定額を記載せず、「遺留分侵害額請求権を行使します。遺留分侵害額はおって計算します。」のように記載し、具体的な金額は後で確定させる形でも構いません。
ただし、計算が済んでいるなら明記した方が相手も対応しやすいでしょう。 - 送付先
請求相手を特定するため、相手方の正確な住所・氏名を記載する必要があります。 - 部数
通常、相手方送付用、郵便局保管用、差出人保管用の合計3部を作成します。 - 手続き
郵便局の窓口で手続きが必要です。
電子内容証明サービス(e内容証明)を利用すれば、オンラインで24時間送付手続きが可能です。
内容証明郵便の書き方については、日本郵便のウェブサイトなどで確認できますが、記載内容に不備があると請求の効力が認められないリスクもあるため、慎重な作成が求められます。
ステップ3:相手方との交渉(話し合い)
内容証明郵便を送付し、相手方に請求の意思が伝わったら、次は具体的な支払いについて相手方と話し合い(交渉)を行います。
交渉では、主に以下の点を話し合うことになります。
- 遺留分侵害額の算定根拠
ご自身が計算した遺留分侵害額の根拠(財産目録、評価額、計算方法など)を示し、相手方の理解を求めます。
相手方から反論があれば、その根拠を確認し、再度計算や検討を行います。 - 支払方法・支払時期
一括で支払うのか、分割にするのか、いつまでに支払うのかなどを具体的に決めます。
相手方が請求に応じ、円満に話し合いがまとまれば、それが最も望ましい解決です。
合意に至った場合には、後日の紛争を防ぐため、必ず合意書を作成し、署名・捺印しておきましょう。
【自分で交渉する際の注意点】
- 感情的になりやすい
相続問題、特にお金が絡む遺留分の話し合いは、親族間であっても感情的な対立が生じやすいものです。冷静さを保ち、論理的に話し合いを進めることが重要ですが、ご自身が当事者である場合、感情的になってしまい、交渉がこじれる可能性があります。 - 相手方が話し合いに応じない可能性
請求を無視されたり、高圧的な態度を取られたりして、そもそも話し合いにならないケースもあります。 - 法律知識の不足
相手方から法的な主張や反論があった場合に、適切に対応できない可能性があります。
ステップ4:家庭裁判所での調停
当事者間の話し合いで解決しない場合、次の手段として、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立てることになります。
調停は、裁判官(または調停官)1名と、民間から選ばれた有識者である調停委員2名以上で構成される調停委員会が間に入り、当事者双方の言い分を聞きながら、合意を目指して話し合いを進める手続きです。
【調停の特徴】
- 非公開
手続きは非公開で行われます。 - 話し合いが基本
あくまで当事者の合意による解決を目指します。調停委員が解決案を提示することはありますが、強制力はありません。 - 比較的簡易な手続き
訴訟に比べると、手続きは比較的簡易で、費用も低額です。
【自分で調停を進める際の注意点】
- 申立ての手続き
申立書の作成や、戸籍謄本、財産に関する資料などの必要書類の準備・提出を自分で行う必要があります。 - 主張・立証
調停期日には裁判所に出頭し、調停委員に対して、自身の主張(遺留分侵害額の計算根拠など)を分かりやすく説明し、それを裏付ける資料を提出する必要があります。相手方の主張に対して、法的な観点から的確に反論することも求められます。 - 長期化の可能性
相手方との主張が平行線をたどる場合、調停が数ヶ月から1年以上に及ぶこともあります。
調停で合意が成立すると、その内容をまとめた「調停調書」が作成されます。
調停調書は確定判決と同じ効力を持ちますので、相手が合意した金額を支払わない場合、強制執行ができます。
ステップ5:地方裁判所での訴訟
調停でも合意に至らない場合(調停不成立)、最終的な解決手段として、地方裁判所に「遺留分侵害額請求訴訟」を提起することになります。
訴訟は、当事者が互いに主張と証拠を提出し、最終的に裁判官が法と証拠に基づいて判決を下す手続きです。
【訴訟の特徴】
- 公開の法廷
原則として、公開の法廷で行われます。 - 厳格な手続き
民事訴訟法のルールに従って進められます。主張は「準備書面」という書面で行い、証拠を提出する必要があります。
証人尋問や本人尋問が行われることもあります。 - 最終的な判断
話し合いで解決しない場合、裁判所が判決という形で最終的な判断を示します。
【自分で訴訟を進める際の注意点】
- 手続きの複雑さ
訴状の作成、証拠の収集・提出、準備書面の作成、期日への出頭など、極めて専門的かつ複雑な手続きを自分で行う必要があります。
法律の知識がない場合、手続きを適切に進めることはかなり大変です。 - 立証責任
原則として、権利を主張する側(遺留分を請求する側)が、遺留分侵害の事実や侵害額などを証拠に基づいて証明する必要があります(立証責任)。 - 時間と労力
訴訟は長期化することが多く、多くの時間と精神的な負担がかかります。 - 相手方が弁護士を立てる可能性
訴訟になると、相手方も弁護士に依頼する可能性が高まります。
弁護士と法的な議論を対等に行うことは、一般の方には極めて困難です。
【重要】遺留分侵害額請求権の時効(タイムリミット)
遺留分侵害額請求権には、時効があります。
この期間を過ぎてしまうと、権利を行使できなくなってしまうため、十分に注意が必要です。
民法 第1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。(出典:e-Gov法令検索 民法)
具体的には、以下の2つの期間制限があります。
- 遺留分権利者が、①相続の開始(被相続人の死亡)と ②遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの両方を知った時から1年間
- 相続開始の時から10年間
このどちらか早い方が到来すると、時効により権利が消滅してしまいます。
特に「知った時から1年間」という期間は、意外と早く経過してしまう可能性があります。
具体的には、「遺言書の内容を知った」「特定の財産が生前に贈与されていたことを知った」時点からカウントダウンが始まります。
自分で手続きを進めようとして、計算や調査に手間取っているうちに1年が経過してしまうケースも考えられます。
1年の時効を止めるためには、期間内に相手方に対して明確な請求の意思表示(通常は内容証明郵便)をする必要があります。
遺留分の請求を検討している場合は、まず時効の起算点と残りの猶予期間を確認し、迅速に行動を開始することが非常に重要です。
遺留分の請求は自分でできるか?
弁護士への依頼は義務ではありませんので、法律上は、遺留分侵害額請求の手続きを弁護士に依頼せず、ご自身で行うことは可能です。
しかし、「可能であること」と「実際にスムーズかつ適切に行えること」は別問題です。
これまで見てきたように、遺留分請求の手続きには、以下のような専門的な知識やスキル、そして相応の時間と労力が必要となります。
- 正確な遺留分侵害額の計算能力(財産調査、評価、特別受益の判断を含む)
- 法律に基づいた適切な手続きの知識(内容証明郵便の作成、時効管理、調停・訴訟の手続き)
- 相手方との冷静な交渉能力
- 調停や訴訟における主張・立証能力
- 手続きにかかる時間と精神的な負担への耐性
これらのすべてをご自身で、しかも感情的な対立が生じやすい親族間の問題において、適切に行うことは、決して容易ではありません。
ご自身の状況(財産の複雑さ、相手方との関係性、ご自身の時間的・精神的余裕など)を客観的に見極め、ご自身で対応可能かどうかを慎重に判断する必要があります。
弁護士に依頼しない場合のデメリット・リスク
遺留分請求の手続きを弁護士に依頼せずに自分で行う場合、具体的にどのようなデメリットやリスクがあるのでしょうか。
遺留分の請求を自分でする場合の注意点は、以下のとおりです。
- 計算ミスによる請求漏れのリスク
財産調査や評価、特別受益の判断を誤り、本来請求できるはずの遺留分侵害額よりも少ない金額しか請求できない可能性があります。 - 時効期間の徒過リスク
手続きに手間取ったり、相手方との交渉が長引いたりしている間に、1年の時効期間が経過してしまい、権利そのものを失ってしまう危険性があります。 - 手続き上のミスのリスク
内容証明郵便の記載不備、調停・訴訟における提出書類の不備や主張・立証の不足など、手続き上のミスにより、不利な結果を招く可能性があります。 - 証拠収集の困難
特に相手方が協力的でない場合、生前の贈与に関する資料や、相手方が管理している財産に関する情報を収集するのは非常に困難です。
弁護士であれば、弁護士会照会などの法的な手段を用いて調査を進めることができます。 - 交渉が不利になる可能性
感情的になりやすく、冷静な交渉が難しい場合があります。
また、相手方に法律知識があったり、相手方が弁護士を立てたりした場合、法的な議論で太刀打ちできず、不利な条件で合意せざるを得なくなる可能性があります。 - 精神的・時間的負担が大きい
慣れない手続きや相手方との直接交渉は、精神的に大きなストレスとなります。
また、書類作成や裁判所への出頭など、多くの時間を費やすことになります。 - 紛争の長期化・泥沼化のリスク
適切な対応ができないことで、かえって紛争がこじれ、解決までに長い時間がかかってしまう可能性があります。
これらのデメリットを考慮すると、費用を節約しようとして自分で手続きを進めた結果、かえって時間や労力を浪費し、得られるはずだった利益を失ってしまうという事態も起こり得ます。
弁護士への依頼を特に検討すべきケース
以下のようなケースでは、ご自身で対応するリスクが高く、弁護士への依頼を積極的に検討することをおすすめします。
- 遺産の内容が複雑・多岐にわたる場合
不動産(特に複数の物件や共有不動産)、非上場株式、事業用資産、海外資産などが含まれる場合、財産評価や調査が複雑になります。 - 遺産の全体像が不明な場合
被相続人の財産がどれだけあるのか分からない、隠されている可能性がある場合。 - 生前贈与(特別受益)の有無や金額について争いがある場合
過去の贈与の事実認定や評価、特別受益に該当するかどうかの判断が難しい場合。 - 相手方との関係が悪く、話し合いが困難と予想される場合
感情的な対立が激しい、相手方が高圧的である、または話し合いを拒否している場合。 - 相手方がすでに弁護士に依頼している場合
法的な知識や交渉力で対等に渡り合うためには、こちらも専門家である弁護士に依頼するのが賢明です。 - 時効期間(1年)が迫っている場合
迅速かつ確実に請求手続きを進める必要があるため、専門家のサポートが不可欠です。 - ご自身で手続きを進める時間がない、または精神的な負担が大きいと感じる場合
無理にご自身で抱え込まず、専門家に任せることで、心身の健康を保つことができます。 - 調停や訴訟になる可能性が高いと見込まれる場合
法的な手続きに適切に対応するためには、早期に弁護士に相談・依頼することが望ましいです。
まとめ:ご自身の状況に合わせた最適な選択を
今回は、遺留分の請求をご自身で行う場合の流れや注意点、そしてデメリットやリスクについて解説しました。
遺留分の請求は、法律上、ご自身で行うことが可能です。
しかし、その手続きは、正確な計算、法的な知識、交渉力、そして多大な時間と労力を要します。
特に、財産内容が複雑な場合や、相手方との関係が良好でない場合には、多くの困難が伴います。
ご自身で手続きを進めることを検討する際には、計算の正確性、時効管理、手続きの複雑さ、相手方との交渉、精神的・時間的負担といった点を十分に考慮する必要があります。
弁護士に依頼しない場合のデメリットやリスクも念頭に置くことが大切です。
一方で、弁護士に依頼すれば、専門的な知識と経験に基づき、正確かつスムーズに手続きを進めることができ、ご自身の負担を大幅に軽減できます。
特に複雑な事案や紛争性が高い事案では、弁護士のサポートが不可欠となるでしょう。
遺留分は、法律で認められた正当な権利です。
不公平な遺言によって権利が侵害されているのであれば、泣き寝入りする必要はありません。
ご自身の状況を冷静に見極め、メリット・デメリットを比較検討した上で、ご自身で手続きを進めるのか、専門家である弁護士に依頼するのか、最適な方法を選択してください。この記事が、その判断の一助となれば幸いです。

