特別受益に当たらない生前贈与があるって本当?生前贈与で相続分を減らさずに済む方法を弁護士が解説
生前贈与は遺産に持ち戻され、相続分が減ると考える方が多くおられます。しかし、遺産に持ち戻されるのは、特別受益に当たる生前贈与だけであり、あらゆる生前贈与が遺産に持ち戻されるわけではありません。この記事を読めば、【特別受益に当たらない生前贈与】があることが分かり、遺産分割において、何となくの感覚で相続分を減らさずに済むようになります。
生前贈与は特別受益に当たり、相続分が減るのが原則
遺産分割では、○分の1という法定相続分で分けるのが原則です。
しかし、特定の相続人だけが生前贈与をもらっている場合、残った遺産を単純に○分の1で分けると、生前贈与の分だけ不公平になります。
亡くなった親からもらった生前贈与は、いわゆる特別受益として、法定相続分を修正する特殊な要素となります。
これを【特別受益の持ち戻し】といい、先に生前贈与でもらった分、「原則として」、遺産分割の場面では相続分が減ります。
そのため、親からお金をもらっていたり、利益を得ていたりしていた場合、遺産分割の場面で、他の兄弟から、特別受益だから相続分が減ると主張されることがよくあります。
そして、この原則論だけしか知らず、何となくの感覚で、特別受益として相続分を減らす必要があると誤解する相続人もおられます。
遺産分割の注意点は【生前贈与≠特別受益】
しかし、そもそも生前贈与=特別受益なのでしょうか?
答えは、ノーです。
生前贈与であれば、なんでも特別受益になるわけではありません。
法律では、
【婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としての生前贈与】
が特別受益とされています(民法903条1項)。
逆に言えば、婚姻、養子縁組、生計の資本ではない生前贈与であれば、特別受益にはならないということです。
問題は、具体的にどのような生前贈与が特別受益に当たるかです。
特別受益になるかどうかの重要ポイントは、
【遺産の前渡し】なのか
【親の扶養の範囲】なのか
です。
つまり、
遺産の前渡し→特別受益になる
扶養の範囲→特別受益にならない
ということです。
しかし、遺産の前渡しなのか扶養の範囲なのかを切り分ける明確な基準は必ずしもありません。
特別受益にあたるかどうかは、過去の裁判例などを参考にしつつ、生前贈与の金額や趣旨などから個別具体的に検討する必要があります。
そして、裁判であれば、特別受益に当たらないことを裏付ける証拠も提示する必要があります。
特別受益に当たるかどうかでよく問題となるもの
建物をただで使用していた場合(建物の無償使用)
法律相談でよくあるのが、相続人の一人が親と同居しており、ただで実家に住んでいたことが特別受益になるのではないかという質問です。
居住の利益を得ているので、特別受益になると考えがちですが、親の実家に同居して家賃が浮いたとしても、相続人自身が独立の占有権原を与えられたわけではありません。
また、建物の場合、土地と比べて居住者を退去させるのは比較的容易です。
ただで使わせたとしても、必ずしも建物の法的な価値が減るとはいえません。
実際、不動産鑑定評価基準でも、建物の使用借権(ただで使用する権利)の評価はゼロであり、贈与と同じように考えることはできません。
さらに、住む場所を提供してあげたということで、遺産の前渡しというより、親族間の恩恵や扶養の要素が強くなります。
そのため、相続人の一人が親の建物をただで使用していたとしても、原則として、特別受益にはなりません。
過去の裁判例でも、特別受益にはならないと判断するものが多数あります。
ここは誤解される方が非常に多いところですが、利益を得ていれば何でも特別受益になるわけではないということです。
なお、収益物件として賃貸している建物をあえてただで使用させたなどの特殊事情があれば、建物の無償使用が特別受益になる可能性もないわけではありません。
しかし、建物を使用させること自体は贈与ではありませんので、建物の無償使用を特別受益として主張する場合、個別事情をかなり工夫して法律構成する必要があろうかと思います。
土地をただで使用していた場合(土地の無償使用)
土地の無償使用については、建物の場合とは逆に、そもそも特別受益の問題に気が付かない方が多くおられます。
たしかに、親の土地をただで使わせてもらうことは、厳密には贈与ではありません。
しかし、土地の使用借権(ただで使用する権利)には、財産的な価値があります。
実際、不動産鑑定評価基準でも、土地の使用借権は、建物の堅固非堅固などの要素を考慮し、更地価格の1〜3割の価値と評価されます。
使用権が付く分、逆に土地の価値は減りますので、減った価値相当額が土地の使用者に移ったと考えられます(贈与類似)。
親の土地に自宅を建て、ただで土地を使用していた場合が典型ですが、土地の使用借権の贈与を受けたものとして、使用借権の評価額(更地価格の1〜3割程度)が特別受益になります。
死亡保険金
死亡保険金が特別受益に当たるのではないかということも、法律相談でよく聞かれる質問の一つです。
被相続人の死亡により、特定の相続人が現金を受領しますので、一見、特別受益として遺産に持ち戻さなければ不公平であるようにも思われます。
しかし、死亡保険金は、被相続人からもらうお金ではなく、【相続人固有の権利】として、保険会社からもらうお金です。
死亡保険金の保険料も、被相続人から保険会社に支払うお金です。
いずれも被相続人から贈与を受けるわけではありませんので、法的な発想として、特別受益にならないのが大原則です。
それでは、死亡保険金であれば、常に特別受益には当たらないのでしょうか?
答えは、ノーです。
最高裁判所は、
【保険金の受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が到底是認することができないほど著しく不公平な場合】
には、例外的に特別受益になると判断しています(最決平成16年10月29日)。
この例外にあたるかどうかは、
- 遺産総額に対する保険金の割合
- 同居の有無
- 介護等での貢献
- 相続人・被相続人同士の関係
- 各相続人の生活実態
など、様々な事情をトータルで判断します。
つまり、死亡保険が特別受益になると主張したい相続人は、上記の事情を裏付けにより証明する必要があります。
裁判例の傾向から、一般的には、①の遺産総額に対する保険金の割合が重要で、6割を超えると、特別受益になる可能性が高くなると言われています。
ただし、死亡保険金が特別受益になるのは極めて例外的なケースですので、【著しく不公平】のハードルは高いです(ただの不公平では足りません)。
そのため、死亡保険をもらった相続人であれば、基本、特別受益には当たらないというスタンスで大丈夫です。
他の相続人から特別受益だと主張されても、例外的な事情を証明しなければならないのは相手ですので、慌てる必要はありません。
生活費の援助・こづかい
親から数万円単位の現金を継続してもらっていた相続人がいる場合、それを積算した金額が特別受益になるのではないかと聞かれる場合もあります。
たしかに、数万円単位の現金であっても、法的には贈与に当たります。
しかし、数万円単位の現金であれば、生計の資本というよりも、こづかいにすぎず、親族間の扶養義務の範囲であるとして、特別受益に当たらないと考えるのが一般的です。
援助期間が長期間に及び、積算すると多額になったとしても、あくまでも一つ一つの援助はいずれも扶養の範囲であり、積算した金額が特別受益になるわけではありません。
逆に、1回の金額が大きい場合、その援助は単なるこづかいとはいえず、「生計の資本」としての特別受益になる可能性があります。
なお、平均的な家族に関しては、裁判例において、10万円を超えるかどうかを基準に考える傾向にあります。
他方、相応の資産を有する家族に関しては、100万円を基準にした裁判例もあります。
結局、遺産の総額や被相続人の収入状況等に応じてケースバイケースといえ、個別具体的な検討が必要ということになります。
大学の学費の援助
昔はともかく、今は、大学への進学率が高くなっています。
特定の相続人に対する大学の学費の援助は、原則として親の扶養の範囲となり、特別受益にはなりません。
公立・私立、海外留学、大学院進学などにより、学費に差が生じたとしても同様です。
しかし、例外的に、私立大学の医学部や歯学部など、入学金や学費が特に高額な場合には、特別受益に当たる可能性があります。
もっとも、親が開業医で、後継者となることを親が希望していた場合には、特別受益にならない可能性が高くなります。
実際、扶養の範囲とした裁判例もあります。
住宅購入資金の援助
住宅は生活の基礎となる財産ですし、援助の金額も大きくなるのが通常です。
住宅購入資金の援助は、【生計の資本】の贈与として、特別受益になるでしょう。
事業資金の援助
経営者にとって、事業は生計の基礎となり、援助の金額も大きくなるのが通常です。
事業資金の援助は、【生計の資本】の贈与として、特別受益になるでしょう。
ただし、金額がそこまで大きくなく、実質的には生活費の援助といえるのであれば、扶養の範囲となり、特別受益にはならないでしょう。
借金の立替払い
親が子の借金(債務)を代わりに支払った場合、本来、親は子に立替払い分を請求できます(これを「求償権」といいます。)。
しかし、立替分の請求をせずに長期間放置していれば、求償権の放棄=債務免除になります。
そのような場合には、実質的に生前贈与をしたのと変わりがありません。
立替えの金額が相当額であれば、【生計の資本】の贈与として、特別受益になるでしょう。
結婚式費用の援助・結婚支度金の贈与
結婚式費用の援助については、親から子への贈与ではありませんし、両親・親戚一同にとっての儀式としての性格もありますので、特別受益にはならないと考えるのが一般的です。
結婚支度金の贈与については、結婚後の生計の援助ですので、金額によっては特別受益になる可能性はあります。
過去の裁判例でも、特別受益に当たると判断するものもあります。
しかし、被相続人の資産状況や社会的な地位等に照らし、扶養義務の範囲に属するものは特別受益に当たらないとする裁判例の傾向です。
そのため、金額が極めて高額だったり、相続人間に看過しがたい不均衡が生じたりしない限り、特別受益には当たらないと考えるのが一般的です。
お祝い金
新築祝いや入学祝など通常の援助の範囲内でなされたお祝いは、扶養義務に基づく援助ないし冠婚葬祭という儀礼の範囲であり、特別受益にはなりません。
特別受益に当たっても、例外的に持ち戻しが免除される場合がある
生前贈与が特別受益に当たっても、例外的に特別受益の持ち戻しが免除され、相続分を維持できる場合があります。
亡くなった人が、【持ち戻し免除の意思表示】(民法903条3項)をした場合です。
簡単に言えば、
【生前贈与をした親が相続分を減らさなくてもいいよと考えていた】
場合です。
たとえば、土地をただで使用していた場合や住宅購入資金を援助してもらった場合、基本的に特別受益に当たりますが、その代わりに親の面倒を見るという負担を負っていたのであれば、特別受益と親の面倒との間に対価関係が生じます。
このような場合には、黙示的に持ち戻し免除の意思表示があったとも考えられ、相続分を維持できる可能性があります。
その他のケースでも、特別受益には当たるけど、個別具体的な事情を加味すれば、黙示的に【持ち戻し免除の意思表示】が認められる場合はあり得ます。
つまり、まずは
①【生前贈与が特別受益になるかどうか】
を検討し、特別受益には当たりそうだとしても、
②【持ち戻し免除の意思表示があったかどうか】
を検討しなければ、生前贈与で相続分が減るかどうかの結論は出ないということになります。
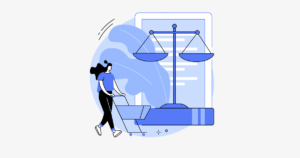
重要なことは個別具体的な分析と検討
生前贈与なのに特別受益に当たらないものがあることを知っておくだけでも、何となくの感覚で相続分を減らすことを避けられます。
しかし、実際に特別受益の持ち戻しをする必要があるかどうかは、特別受益の持ち戻し免除の意思表示も含めると、一般論で白黒をつけることはできず、個別具体的な分析と検討が極めて重要になります。
特に例外的な主張をしたい場合、原則をひっくり返すだけの説得的な論理や証拠が必要になりますので、弁護士に相談することを検討した方がいいでしょう。

