いらない土地の共有持分を相続してしまった… 他の共有者に共有持分を買い取らせる方法
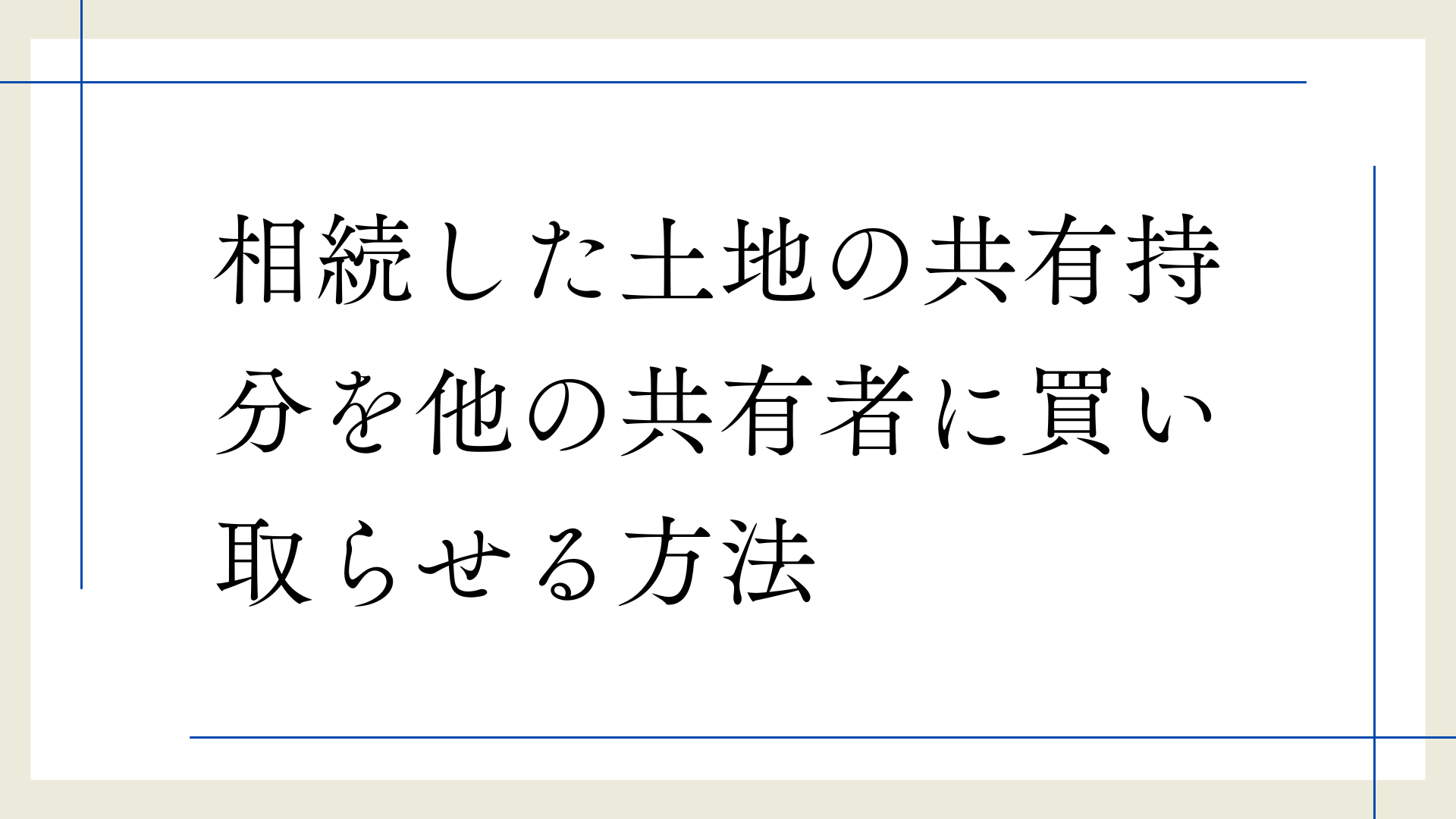
相続した「いらない土地」、共有持分をどうする?
親などが亡くなり、予期せず土地を相続することがあります。
特に、兄弟姉妹や他の親族と一緒に、一つの土地を共同で相続するケースは少なくありません。
これが「共有」の状態です。
しかし、相続した土地が必ずしもご自身にとって必要なものとは限りません。
「利用する予定もないし、管理も面倒」「できれば現金化したい」と考えても、他の共有者が売却に反対していたり、そもそも話し合いに応じてくれなかったりすると、身動きが取れなくなってしまいます。
特に、ご自身が使ってもいない土地の共有持分を、他の共有者に買い取ってもらいたいのに拒否されてしまうと、途方に暮れてしまうかもしれません。
しかし、他の共有者があなたの持分の買い取りを拒否したからといって、諦める必要はありません。
このような膠着状態を打開するための法的な手続きも用意されています。
この記事では、相続によって取得した不要な土地の共有持分について、他の共有者に買い取ってもらうための交渉方法から、交渉が不調に終わった場合の法的な解決策、特に「共有物分割請求訴訟」を通じて買い取りを実現する可能性まで、具体的なステップと注意点を分かりやすく解説します。
法的な知識を身につけることで、ご自身の権利を理解し、問題解決に向けた具体的な一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。
相続で取得した土地の「共有持分」とその問題点
まず、相続によって土地を共有している状態、そして「共有持分」とは具体的にどのようなものか、基本的な点を押さえておきましょう。
共有持分とは?
共有持分とは、一つの不動産(この場合は土地)を複数の人が共同で所有している場合に、それぞれの人が持っている所有権の割合のことを指します。
よくある誤解は、「土地のこの部分が自分のもの」というように、物理的に分割された区画を所有していると考えることですが、そうではありません。
共有持分は、土地全体に対して「何分のいくつ」という割合で権利を持っている状態です。
例えば、3人の兄弟が土地を均等に相続した場合、それぞれが土地全体に対して「3分の1」の共有持分を持つことになります。
特定の場所を排他的に所有しているわけではなく、土地全体に対して3分の1の権利を持っているということです。
相続による共有状態の発生
土地の共有状態が発生することは、相続においてしばしば見られます。
例えば、以下のようなケースです。
- 被相続人が所有していた土地が共有持分のみであり、それを相続する場合
- 遺言で土地を共有にすると指定されていた場合
- 相続後もきょうだい間で賃料を分配するため、遺産分割協議で駐車場を共有にする場合
共有状態が引き起こす具体的な問題点
共有持分を持つこと自体が問題なのではなく、共有状態であるがゆえに生じる実務上の困難さが問題となります。
具体的には、以下のような問題です。
- 管理・費用の問題
土地を維持管理するためには、固定資産税の納付や、必要に応じた修繕、草刈りなどが必要です。
これらの費用は、原則として共有持分に応じて各共有者が負担すべきものですが、実際には連絡が取りやすい人や、管理に積極的な人だけが立て替えているケースも多く見られます。
また、共有物の管理に関する事項は、共有者の持分の価格に従い、その過半数で決定するとされています(民法第252条)。しかし、どのような管理を行うかについて、共有者間で意見がまとまらないこともあります。 - 利用・活用の困難
共有状態の土地を有効活用しようとしても、制約が多くなります。
例えば、駐車場として整備したり、賃貸したりすることは「管理行為」として持分割合の過半数の同意で可能です。
しかし、土地を更地にして売却したり、新たに建物を建築したりするような「変更行為」や「処分行為」は、他の共有者全員の同意がなければ行うことができません(民法第251条)。
一人でも反対する共有者がいれば、土地を有効活用したり、高値で売却したりする道が閉ざされてしまうのです。 - ご自身の持分だけの売却の難しさ
法律上は、ご自身の共有持分だけを第三者に売却することは可能です。
しかし、現実には買い手を見つけることは困難です。
なぜなら、購入者にとっては、他の共有者との間で将来的に管理や処分に関する意見調整が必要になるなど、複雑な権利関係に足を踏み入れることになるからです。
そのため、もし買い手が見つかったとしても、通常の市場価格よりも大幅に低い価格(いわゆる「訳あり物件」としての価格)になってしまうことがほとんどです。
この現実が、他の共有者への買い取り請求や、後述する共有物分割請求という手段の重要性を高めています。 - 共有者間の紛争リスク: 相続をきっかけに共有者となった人々は、必ずしも仲が良いとは限りません。また、それぞれ経済状況や土地に対する考え方、将来設計も異なります。「売りたい人」と「持ち続けたい人」、「活用したい人」と「現状維持でいい人」など、意見の対立は避けられない場合があり、これが深刻な親族間の紛争に発展するケースも少なくありません。
このように、共有持分は、一見すると資産の一部であるものの、その管理、活用、処分のいずれにおいても多くの制約と困難を伴う可能性があるのです。
まずは交渉から:他の共有者に対する共有持分の買取交渉
共有持分を現金化したいと考えた場合、最初に取り組むべきは、他の共有者に対してご自身の持分を買い取ってもらうよう交渉することです。
訴訟などの法的手続きは、時間も費用もかかり、精神的な負担も大きいため、まずは話し合いによる円満な解決を目指すのが最善です。
交渉の重要性
交渉は、コストを抑え、時間を節約し、そして何よりも共有者間の人間関係を維持する(あるいは、これ以上悪化させない)ための最も望ましい方法です。
裁判所の介入なしに、当事者間の合意で問題を解決できれば、それに越したことはありません。
交渉に向けた準備
成功する交渉のためには、事前の準備が不可欠です。
- 情報収集
土地に関する書類(登記簿謄本、公図、測量図など)、固定資産税の納税通知書、これまで管理費用を負担した記録など、関連する資料をできる限り集めましょう。 - 適正価格の把握(重要)
交渉を始める前に、ご自身の共有持分が市場でどれくらいの価値を持つのか、現実的な見当をつけておくことが極めて重要です。
固定資産税評価額や相続税評価額を鵜呑みにするのは危険です。
適正な市場価格(時価)を意識することが、公正な交渉の土台となります。 - 交渉相手の状況理解
可能であれば、他の共有者がどのような状況にあるのか(経済状況、土地に対する意向、買い取りを拒否する理由など)を事前に把握しておくと、交渉戦略を立てやすくなります。
効果的な交渉戦略
- 適切なタイミングと場所の選択
感情的にならず、落ち着いて話し合える時間と場所を選びましょう。
電話やメールだけでなく、必要であれば直接会って話す機会を設けることも検討します。 - 明確な提案
ご自身の共有持分を売却したい意思と、買い取りをお願いしたい旨を、具体的かつ丁寧に伝えましょう。
希望する価格を提示する際には、その根拠(市場価格に基づいていることなど)も併せて説明できると説得力が増します。 - 相手の意見に耳を傾ける
なぜ買い取りに難色を示すのか、相手の言い分や懸念事項を注意深く聞きましょう。
一方的に要求を突きつけるのではなく、相手の立場を理解しようと努める姿勢が、合意形成の鍵となります。 - 譲歩と代替案の検討
必ずしも最初の希望額通りでなくても、ある程度の譲歩が可能か、あるいは分割払いなどの代替案を提示できないか検討することも有効です。 - 交渉経緯の記録
いつ、誰と、どのような内容を話し合ったのか、提案内容や相手の反応などを記録しておきましょう。
メールや書面でのやり取りは、後々の証拠としても役立ちます。
これは、万が一交渉が決裂し、法的手続きに進む場合にも重要な資料となります。
交渉は、必ずしも一度でうまくいくとは限りません。
粘り強く、しかし冷静に関係者とコミュニケーションをとることが求められます。
相手が感情的になったり、非協力的な態度をとったりする場合でも、こちらも感情的にならず、あくまで問題解決という目的に焦点を当て続けることが大切です。
土地評価額の注意点:固定資産税評価額・相続税評価額と時価との違い
共有持分の買取交渉や、後述する共有物分割請求において、最も争点となりやすいのが「土地の評価額」です。
特に、相続に関連してよく耳にする「固定資産税評価額」や「相続税評価額(路線価)」を、そのまま売買価格の基準としてしまうと、本来の価値よりも著しく低い価格で持分を手放してしまうリスクがあります。
様々な土地評価額とその目的
土地の価格には、目的によっていくつかの異なる指標が存在します。
- 固定資産税評価額
- 目的
市町村が固定資産税や都市計画税、不動産取得税、登録免許税などを計算するために用いる評価額です。 - 算定方法
総務省が定める固定資産評価基準に基づき、3年ごとに評価替えが行われます。
土地の状況(地目、形状、道路との接面状況など)を考慮しますが、個別の取引事情は反映されません。 - 特徴
一般的に、市場価格(時価)よりも低い水準(目安として時価の7割程度と言われることもありますが、地域や物件により大きく異なります)になることが多いです。 - 関連情報(東京都主税局ホームページ)
固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
- 目的
- 相続税評価額(路線価)
- 目的
国税庁が相続税や贈与税を計算するために用いる評価額です。
市街地では主に「路線価方式」、それ以外の地域では「倍率方式」が用いられます。 - 算定方法
路線価は、主要な道路に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価額で、毎年公表されます。 - 特徴
市場価格の公示価格(国土交通省が公表)の8割程度を目安に設定されると言われていますが、これもあくまで目安であり、実際の市場価格とは乖離があります。
特に、個別の土地の形状や利用制限などは十分に反映されない場合があります。 - 関連情報(国税庁ホームページ)
令和6年分の路線価等について
- 目的
- 時価(実勢価格)
- 目的
実際に不動産市場で、自由な意思を持つ売り手と買い手の間で取引が成立すると想定される価格です。
共有持分の売買交渉や裁判所が共有物分割を命じる際に基準となるのは、この「時価」です。 - 算定方法
不動産市場の需給バランス、周辺の取引事例、土地の形状、立地条件、将来性、法的な規制など、様々な要因を総合的に考慮して決まります。 - 特徴
税金の計算を目的とする評価額とは異なり、現実の取引価格に最も近い価格です。
- 目的
なぜ税務上の評価額と時価は異なるのか?
固定資産税評価額や相続税評価額は、あくまで税金を公平かつ効率的に徴収するという行政目的のために、全国的に統一された基準で画一的に算定されるものです。
そのため、個々の土地が持つ固有の価値(例えば、駅からの距離、日当たり、周辺環境、再開発の可能性など)や、その時々の不動産市場の動向を正確に反映しているわけではありません。
税務上の評価額を基準にするリスク
共有持分の買い取り交渉において、他の共有者から「固定資産税評価額を基準にしよう」「相続税の申告で使った路線価で計算しよう」といった提案がなされることがあります。
しかし、これらの評価額は時価よりも低いことが多いため、安易に同意してしまうと、ご自身の持分の本来の価値に見合わない、不当に安い価格で買い取られてしまう可能性があります。
適正な時価を把握する方法
では、交渉や法的手続きで主張すべき「時価」は、どのように把握すればよいのでしょうか。
- 不動産業者による査定(簡易査定)
近隣の不動産業者に依頼すれば、多くの場合、無料で簡易的な査定を行ってくれます。
周辺の取引事例などを基におおよその市場価格を知る手掛かりにはなりますが、あくまで簡易的なものであり、査定額は業者によってばらつきが出ることがあります。
また、将来的な売却仲介を期待して高めの査定を出す可能性も考慮する必要があります。 - 不動産鑑定士による鑑定評価
不動産鑑定士 は、不動産の経済価値に関する国家資格を持つ専門家です。
不動産鑑定士が作成する 不動産鑑定評価書は、客観的かつ詳細な分析に基づいた、法的な証明力を持つ評価額を示します。
費用はかかりますが、特に共有者間で評価額についての意見が対立している場合や、共有物分割請求訴訟を見据える場合には、極めて有効な手段となります。
裁判所も、共有物分割訴訟においては、不動産鑑定士による鑑定評価を重視する傾向にあります。
鑑定評価書があれば、交渉において「客観的な専門家の意見」として価格の根拠を明確に示すことができ、相手方も無下に低い価格を主張しにくくなります。
以下の表は、これらの評価方法の違いをまとめたものです。
| 評価方法 | 根拠・目的 | 算定方法 | 時価との関係(目安) | 買取・共有物分割での利用 |
|---|---|---|---|---|
| 固定資産税評価額 | 固定資産税等の算定 | 総務省の固定資産評価基準に基づき市町村が決定 | 時価より低いことが多い | 交渉の参考程度。これを基準にすると不利になる可能性が高い。 |
| 相続税評価額(路線価) | 相続税・贈与税の算定 | 国税庁が路線価等に基づき算定 | 時価より低いことが多い | 交渉の参考程度。これを基準にすると不利になる可能性が高い。 |
| 時価(不動産業者査定) | 実際の売買価格の目安 | 周辺取引事例、市場動向等を基に業者が簡易査定 | 時価に近いが、ばらつきあり | 交渉の初期段階での参考。法的拘束力は弱い。 |
| 時価(不動産鑑定評価) | 客観的な経済価値の判定(裁判等での基準価格) | 不動産鑑定評価基準に基づき鑑定士が詳細評価 | 最も時価に近いとされる | 交渉及び共有物分割請求訴訟における価格決定の重要な根拠となる。 |
共有持分の買い取り交渉や法的手続きにおいては、安易に税務上の評価額を用いるのではなく、適正な「時価」を把握し、それを基に主張することの重要性を理解しておく必要があります。必要であれば、不動産鑑定士への相談も検討する価値があるでしょう。
交渉が決裂したら:共有物分割請求訴訟という選択肢
他の共有者との間で、共有持分の買い取りに関する交渉がどうしてもまとまらない場合、あるいは相手が話し合いにすら応じてくれない場合、法的な最終手段として「共有物分割請求訴訟」を起こすことができます。
共有物分割請求権とは?
共有状態にある不動産について、各共有者は、原則としていつでも他の共有者に対して、その分割を請求する権利を持っています。
共有物分割請求権は、民法第256条第1項に定められた権利で、他の共有者の同意を必要とせず、共有者であれば誰でも一方的に行使できます。
相続によって意図せず共有者となった場合など、いらない土地の共有関係から離脱する道を開くための重要な制度です。
なお、共有者間で「5年を超えない期間内は分割しない」という特約を結んでいる場合、その期間中は請求できません(民法256条1項ただし書)。しかし、相続で共有になったケースにおいて、そのような特約が存在することは稀です。
共有物分割請求訴訟の流れ(概要)
共有物分割請求は、まずは当事者間の協議(話し合い)によって行うことが原則です。
しかし、協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、裁判所に訴訟を提起することになります(民法258条1項)。
訴訟は、対象となる不動産の所在地を管轄する地方裁判所(または簡易裁判所)に訴状を提出することから始まります。
その後、訴状が他の共有者(被告)に送達され、被告からの答弁書の提出、口頭弁論期日での主張・立証(証拠調べ)、和解の試みなどを経て、最終的に裁判所が分割方法を命じる判決を下します。
共有物分割請求訴訟は、専門的な知識や手続きが必要となるため、弁護士に依頼して進めることが多いです。
解決までには、事案の複雑さにもよりますが、1年~2年程度かかることもあります。
裁判所が命じる分割方法
共有物分割請求訴訟において、裁判所は、当事者の主張や証拠、不動産の性質、共有者間の利害関係などを総合的に考慮し、以下のいずれか、またはこれらを組み合わせた方法で分割を命じます。
- 現物分割
文字通り、共有物を物理的に分割する方法です。
例えば、広い土地であれば、持分割合に応じて土地を分筆(ぶんぴつ:一筆の土地を複数に分けること)することが考えられます。
しかし、一般的な広さの宅地などでは、分筆すると各区画が狭くなりすぎて利用価値が著しく低下したり、建築基準法上の制限で建物を建てられなくなったりすることが多く、現実的には適用が難しいケースが少なくありません。
裁判所も、現物分割によって価格が著しく損なわれる場合には、この方法を採用しません(民法258条3項参照)。 - 換価分割
共有物を第三者に売却し、その売却代金を持分割合に応じて分配する方法です。
裁判所が売却を命じる場合、競売による売却となります(民法258条3項)。
競売は、市場での通常の売却(任意売却)に比べて、売却価格が低くなる傾向があります。
また、この方法では、土地を維持したいと考えている共有者も含め、全ての共有者が土地を手放すことになります。
そのため、共有者全員にとって必ずしも望ましい結果とは言えません。 - 価格賠償
特定の共有者が他の共有者の持分を取得する代わりに、その持分の対価(適正な価格)を支払わせる方法です(民法258条2項2号)。
これは「全面的価格賠償」とも呼ばれ、実質的に、裁判所が共有持分の買い取りを命じることに相当します。
この記事のテーマである「他の共有者に共有持分を買い取らせる」という目的に最も合致するのが、この価格賠償です。
共有者の中に「土地を取得したい」と希望する人がおり、かつ、他の共有者の持分を買い取るだけの資力(支払能力)があると認められる場合、裁判所はこの方法を選択することがあります。
特に、 2023年4月1日に施行された改正民法 では、この価格賠償の要件や手続きに関する規定がより明確化され、裁判所がより柔軟にこの方法を選択しやすくなったと考えられています。
具体的には、共有物の全部または一部を特定の共有者に取得させることが「相当」と認められ、かつ、その共有者に「支払能力」がある場合に、価格賠償による分割が可能であることが明記されました。
共有物分割請求訴訟は、単に「勝つか負けるか」という争いではなく、共有状態という問題を法的に解消するための手続きです。
交渉が決裂した場合でも、この訴訟を通じて、最終的にはご自身の持分を適正な価格で現金化する(価格賠償を実現する)道が開かれていることを知っておくことが重要です。
共有物分割請求訴訟を「交渉材料」にする
共有物分割請求訴訟は、最終的な解決手段ですが、実際に訴訟を提起する「前」の段階で、非常に有効な交渉カードとなり得ます。
つまり、いざとなれば共有物分割請求訴訟を起こすことができるという事実そのものが、買取交渉を有利に進めるための「交渉材料」となるのです。
なぜ訴訟は避けたいのか?(他の共有者の視点)
買い取りを拒否している他の共有者にとって、共有物分割請求訴訟を起こされることは、一般的に避けたい事態です。
その理由はいくつかあります。
- 費用の負担
訴訟になれば、原告(訴えを起こした側)だけでなく、被告(訴えられた側)も弁護士費用や裁判所への予納金などの費用が発生します。望まない出費は避けたいと考えるのが通常です。 - 時間と労力
共有物分割訴訟は、短くても数か月、長ければ2年以上かかることもあり、その間、準備書面の作成や証拠の準備など、多くの時間と精神的な労力を費やすことになります。 - 望まない結果のリスク
裁判所の判断は、必ずしも当事者の希望通りになるとは限りません。
特に、土地を手元に残したいと考えている共有者にとっては、裁判所の命令で土地全体が競売にかけられてしまう「換価分割」のリスクは大きな脅威です。
競売では、市場価格より安くなる可能性が高く、結果的に損をしてしまう恐れがあります。 - 強制的な価格決定
交渉段階では低い評価額を主張していたとしても、訴訟になれば、裁判所は、不動産鑑定などを基に客観的な「時価」を基準に判断します。不当に安い価格での買い取りは認められにくくなります。
訴訟の可能性を「てこ」にした交渉戦略
これらの「訴訟を避けたい」という相手方の心理を理解した上で、交渉に臨むことが有効です。
- 冷静かつ毅然とした態度
感情的に脅すのではなく、「交渉がまとまらないのであれば、法的な権利として共有物分割請求訴訟を提起することも検討せざるを得ません」という意思を、冷静かつ明確に伝えましょう。
これは脅しではなく、法に基づいた次のステップを示すことです。 - 訴訟になった場合のリスクの説明
相手方にとって、訴訟になった場合にどのようなデメリット(費用、時間、代金分割のリスクなど)があるかを具体的に説明することで、交渉による解決のメリットを認識してもらいやすくなります。
特に、「価格賠償」による解決の可能性と、それが適正な市場価格に基づいて行われること、そして最悪の場合は「換価分割」で土地全体を失うリスクがあることを伝えるのは効果的です。 - 早期解決のメリット強調
訴訟を回避し、交渉で合意することのメリット(費用の節約、早期解決、円満な関係維持、予測可能な結果)を強調します。 - 準備状況を示す
すでに不動産鑑定士による簡易査定や正式な鑑定評価を取得している場合、それを示すことで、こちらの本気度と、適正価格に基づいた解決を求めている姿勢を伝えることができます。
「いつでも訴訟に移行できる準備がある」ことを示すことは、相手にプレッシャーを与え、真剣な交渉を促す効果があります。
重要なのは、共有物分割請求権という法的な権利を背景に持ちつつも、あくまで交渉による円満解決を目指す姿勢を示すことです。
訴訟の可能性をちらつかせることで、相手方の計算は「この持分を買い取りたいか?」から、「持分を買い取ることと、訴訟のリスクやコストを天秤にかけて、どちらがマシか?」へと変化する可能性があります。
これにより、当初は拒否していたとしても、買取りに応じる余地が出てきます。
まとめ:「いらない土地の共有持分」問題の解決への道筋
相続によって取得した、ご自身にとっては不要な土地の共有持分。
他の共有者に買い取りを拒否され、どうすればよいか悩んでいる方も多いでしょう。
しかし、これまで見てきたように、解決への道筋は存在します。
本記事のポイントを振り返ってみましょう。
- 共有持分の理解
まず、共有持分とは土地全体に対する割合的な権利であり、管理や処分に共有者全員または過半数の同意が必要となるなど、多くの制約があることを理解します。 - 交渉の試み
最初のステップとして、他の共有者に対し、適正な時価に基づいた持分の買い取りを交渉します。
冷静な対話と事前の準備が重要です。 - 適正な評価額の重要性
固定資産税評価額や相続税評価額は、必ずしも市場の価値を反映していません。
買い取り価格の交渉や法的手続きにおいては、不動産鑑定などを参考に「時価」を把握することが不可欠です。 - 共有物分割請求訴訟という選択肢
交渉が決裂した場合、法的な権利として共有物分割請求訴訟を起こすことができます。 - 訴訟による解決方法
裁判所は、現物分割、換価分割(競売)、または価格賠償(特定の共有者による持分買取り)といった方法で分割を命じます。
特に「価格賠償」は、実質的に共有持分の買取りを実現する手段となり得ます。 - 訴訟を交渉の武器にする
共有物分割請求訴訟を起こせるという事実は、交渉段階において強力な「てこ」となり、相手方に買い取りを促す圧力となります。
他の共有者から買い取りを拒否されたとしても、諦める必要はありません。
共有という状態から抜け出し、ご自身の権利を実現するための法的な手段も残されています。
特に、共有物分割請求訴訟という手続きと、その中でも「価格賠償」という解決方法が存在することを知っておくことは、精神的な支えになるはずです。
この記事で解説した法的知識や手続きの流れを理解することは、ご自身が置かれた状況を客観的に把握し、次に取るべき行動を判断するための第一歩となります。
共有不動産の問題は複雑ですが、適切な知識を持つことで、その解決に向けて着実に前進することができるでしょう。

