「円満相続」のはずが大きな火種に?一次相続で母が父の遺産を全て相続した場合の二次相続におけるリスク
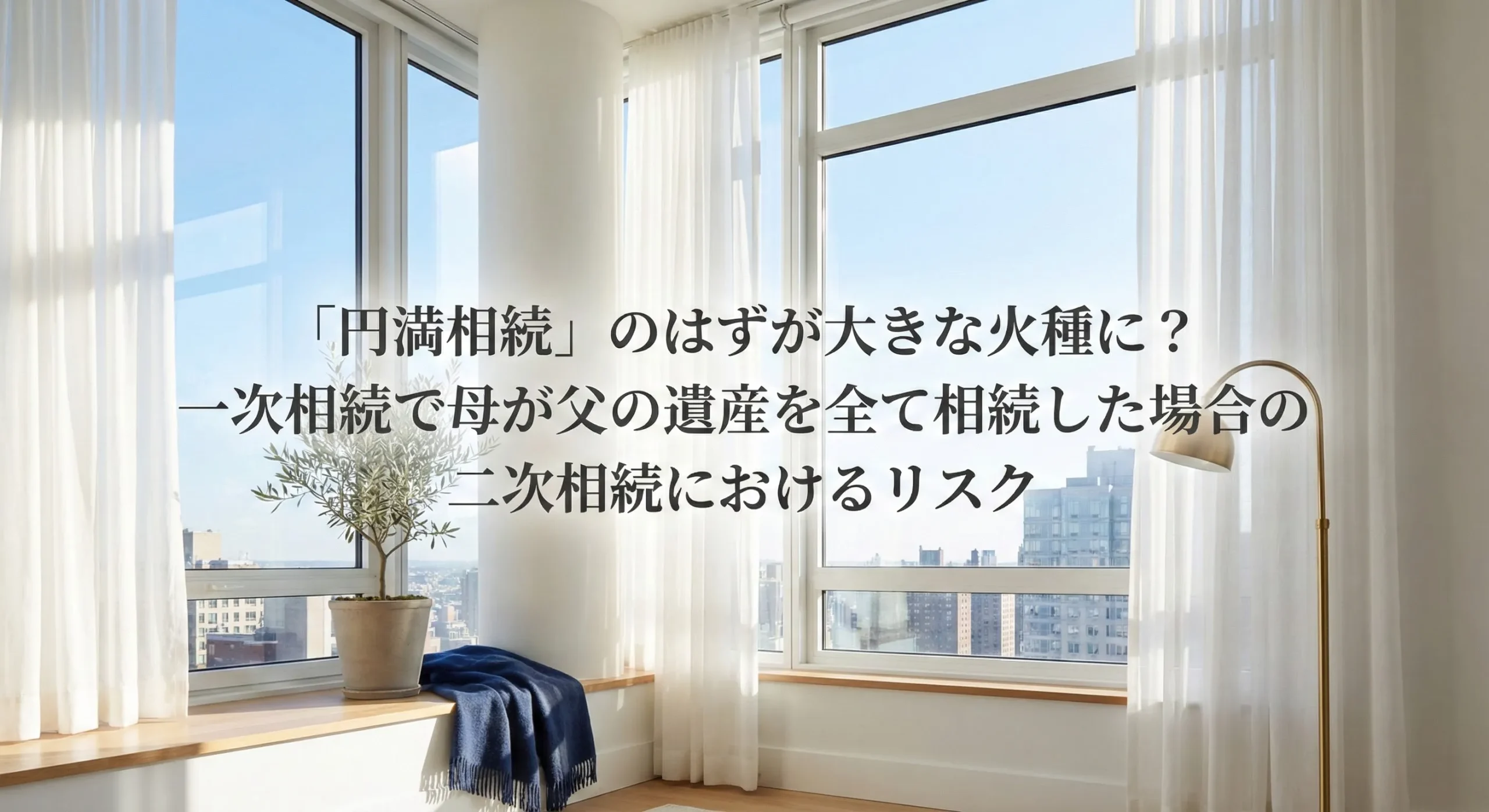
「お父さんの相続だけど、お母さんも高齢だし、生活のこともあるから、とりあえずお母さんに全部相続してもらおう。」
ご家族を想う優しい気持ちから、一次相続の遺産分割協議で、このような考えに至るケースは少なくありません。
また、お母様にお父様の遺産を全て相続してもらうことで、波風を立てずに円満に手続きを終えたい、というお気持ちは非常によく理解できます。
しかし、その時はよかれと思ってやったことが、将来的にご自身やご兄弟姉妹の間で、深刻な問題を引き起こす可能性があることをご存知でしょうか?
特に、「お母様が相続したお父様の遺産が、将来お母様が亡くなったとき(二次相続)にどうなるか」という視点が抜け落ちていると、円満だったはずの相続が、後に大きな火種になりかねません。
この記事では、一次相続でお父様の遺産をお母様が全て相続した場合に生じるリスクとその回避策について、相続に特化した弁護士が詳しく解説します。
1. なぜ「父の遺産を母が全て相続する」という話が出てくるのか?
そもそも、遺産分割協議において、お父様の遺産をお母様が全て相続するという話が出てくるのはなぜでしょうか。
主な理由としては、以下の3点が考えられます。
残された母親の生活への配慮
最も大きな理由は、残されたお母様の生活への配慮でしょう。
長年連れ添った配偶者を亡くした悲しみに加え、経済的な不安まで抱えさせたくない、というお子様たちの優しい気持ちが背景にあります。
「父の財産は、母が安心して暮らすために使うべきだ」「自分たちはまだ働けるから大丈夫」といった考えから、お母様に全てを相続させるという結論に至ることがあります。
また、「遺産分割で揉めたくない」という思いから、一見最も穏便に見えるこの方法が選ばれやすい傾向があります。
「配偶者控除」という相続税の優遇措置
相続税法には、「配偶者控除」という税制上の優遇措置があります。
これは、亡くなった方(被相続人)の配偶者が遺産を相続する場合、以下のいずれか多い金額までは相続税がかからない、というものです。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
法定相続分とは、法律で定められた相続人が遺産を相続できる割合のことです。
たとえば、相続人が配偶者と子の場合、配偶者の法定相続分は遺産の1/2です(民法第900条1号)。
【法定相続分(配偶者と子の場合)】
- 配偶者:1/2
- 子(全員で):1/2(子が複数いる場合は、1/2を均等に分けます)
この「配偶者控除」があるため、一次相続ではお母様に全ての遺産を相続してもらうのが、税金面で最も有利だと考えることがあります。
確かに、一次相続だけを見れば、この制度の恩恵は大きいかもしれません。
しかし、二次相続(お母様の相続)まで考慮に入れると、必ずしもトータルの相続税が軽減されるとは限らない点には注意が必要です。
手続きの簡便さ
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。
不動産、預貯金、株式など、様々な種類の遺産をどのように分けるか具体的に話し合うのは、時間も手間もかかります。
特に、相続人の間で意見がまとまらない場合、協議が長期化し、精神的な負担も大きくなります。
そのような状況を避けるため、「とりあえず、お母さんに全部相続してもらって、手続きを早く終わらせよう」という考えに至ることがあります。これは、一見すると最も手っ取り早い解決策に見えるかもしれません。
しかし、これらの理由で安易にお母様がお父様の遺産を全て相続すると、将来、二次相続の段階で思わぬ問題に直面するリスクがあるのです。
次に、二次相続における具体的なリスクを詳しく見ていきましょう。
二次相続で期待が裏切られるリスクとその理由
一次相続でお母様が全ての遺産を相続した場合、その財産はお母様の固有財産となります。
ここが重要なポイントです。
法的には、もはやお父様の遺産ではなく、お母様の財産として扱われます。
二次相続では相続できると期待していたとしても、その期待は法的に保証されているわけではありません。
お母様は、ご自身の財産を、ご自身の意思で自由に処分できてしまうからです。
では、具体的に、二次相続でどのようなリスクが考えられるでしょうか。
リスク①:使い込みや生前贈与
お母様は、相続した財産をご自身の判断で自由に使うことができます。
生活費はもちろん、趣味や旅行、リフォームなどに使うことも可能です。
また、特定のお子様や、お孫様、あるいは相続人以外の方(例えば、お世話になった方など)に、生前贈与を行う可能性もあります。
生前贈与自体は違法ではありませんが、特定の子や孫だけもらえば、それが将来の紛争の火種となることがあります。
特に、一次相続の際、「いずれ自分たちに財産が戻ってくる」という期待があった場合には、お母様による多額の支出や贈与は、その期待を裏切る形となり、感情的なしこりを残す可能性があります。
リスク②:遺言による相続分の変動
お母様は、遺言書を作成し、誰にどのように相続させるかについて、自由に決めることができます。
たとえ一次相続の際、「将来は子供たちで均等に分けるように」といった口約束があったとしても、法的に有効な遺言書が作成されれば、原則としてその内容が優先されます。
遺言書の内容が、当初の期待と大きく異なる場合、裏切られた気持ちになる上、二次相続では、遺留分請求などの法的な争いに発展する可能性が高まります。
リスク③:母の再婚による相続人の変化
もしお母様が再婚した場合、新しい配偶者も法定相続人となります(民法第890条)。
この場合、お母様の遺産(元々はお父様の遺産だったものを含む)は、お子様たちだけでなく、再婚相手も相続する権利があります(しかも、法定相続分は1/2!)。
つまり、お母様が再婚すると、お子様たちが二次相続で受け取れる遺産が、当初想定していたものより大幅に減少する可能性があるのです。
再婚相手との関係性が良好でない場合、二次相続における遺産分割協議が難航することも考えられます。
リスク④:母の判断能力低下(認知症など)による財産管理の問題
高齢化に伴い、お母様が認知症などにより判断能力が低下する可能性も考慮に入れる必要があります。
判断能力が不十分になると、ご自身で財産を適切に管理することが難しくなります。
このような場合、お母様に成年後見人をつける必要が出てくる可能性があります。
成年後見人は、本人の財産を管理し、法律行為を代理する役割を担いますが、その選任や職務遂行には家庭裁判所が関与します。
成年後見人には、親族が選ばれることもありますが、弁護士や司法書士などの専門家が選任されるケースも少なくありません。
後見人は、あくまでもお母様ご本人の利益のために財産を管理・処分するため、お子様たちの「将来の相続」への期待とは異なる判断をする可能性があります。
例えば、お母様の施設入所費用を捻出するために、お子様たちが相続することを期待していた不動産が売却される、といった事態も起こりえます。
一次相続でお子様たちが財産を相続していれば、少なくともその部分については、後見制度の影響を受けずに済みます。
リスク⑤:二次相続における相続税の増加
「配偶者控除」があるため、一次相続では相続税が大幅に軽減される、あるいはゼロになるケースが多いことは前述の通りです。
しかし、二次相続では配偶者がいないため、「配偶者控除」は適用されません。
二次相続では、原則どおり、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える部分について相続税が課税されます。
しかし、一次相続でお母様がお父様の遺産を全て相続した場合、お母様の財産が膨らみ、二次相続における課税対象額が大きくなる可能性があります。
また、二次相続では、法定相続人の数が一次相続(配偶者+子)より少なくなることが通常であり、その分、基礎控除額も小さくなります。
さらに、不動産などの分けにくい財産がお母様に集中した場合、二次相続の相続税の納税資金を確保するため、その不動産を売却せざるを得なくなる、といった問題も生じやすくなります。
一次相続、二次相続を通じたトータルの相続税負担を考えると、一次相続でお子様たちもある程度遺産を相続しておいた方が、結果的に税負担が軽減されるケースも少なくありません。
【表:一次相続で父の遺産を母が全て相続するリスクまとめ】
| リスクの種類 | 具体的な内容 | なぜ問題になるか |
|---|---|---|
| ① 生前の使い込み・贈与 | 母が自身の判断で財産を消費・贈与する | 子の期待(二次相続での取得分)が裏切られ、不公平感から紛争へ発展するリスク |
| ② 遺言による相続分の変動 | 母が遺言で特定の子や第三者に財産を遺贈・寄付する | 子の期待と異なる相続割合となり、遺留分請求など法的な争いに発展するリスク |
| ③ 再婚による相続人の変化 | 母の再婚相手も法定相続人となり、相続分が発生する | 子が二次相続で取得できる遺産の割合が大幅に減少し、遺産分割協議が難航するリスク |
| ④ 判断能力低下による財産管理問題 | 認知症等で成年後見人が選任され、財産管理・処分が行われる | 後見人が本人の利益を最優先するため、子の期待とは異なる財産処分(不動産売却など)が行われるリスク |
| ⑤ 二次相続での相続税負担増 | 母に財産が集中し、二次相続での課税対象額が増加。配偶者の税額軽減は適用されない。基礎控除額も減少する可能性がある。 | 一次・二次トータルでの相続税負担が増加する可能性。納税資金確保のため、望まない財産売却が必要になるリスク |
では、二次相続におけるこれらのリスクを回避するためには、どのようにすればいいのでしょうか。
一次相続で「自分の相続分」を確保することの重要性
二次相続における様々なリスクを回避し、ご自身の権利を確実に守るための最も有効な方法は、
一次相続の段階で、ご自身も法定相続分に応じた遺産を相続しておくこと
です。
法定相続分をベースとした遺産分割協議
相続人には法律で認められた相続分(法定相続分)がありますが、これはあくまでも原則です。
相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で遺産分割をすることもできます(民法第907条1項)。
しかし、二次相続のリスクを考慮するのであれば、一次相続の遺産分割協議において、安易に法定相続分を変えるのではなく、ご自身の法定相続分を確保することを基本線として考えるべきです。
もちろん、お母様の生活に対する配慮も大切です。
しかし、その場合は、以下のような調整方法も考えられます。
- 相続する遺産の種類で調整する
- お母様には、当面の生活に必要な預貯金や、現在居住している自宅不動産を相続してもらう。
- お子様たちは、賃貸不動産や株式、遠方の土地など、すぐには生活に必要ない財産を相続する。
- 所有と利用を分ける
- 自宅不動産はお子様が相続したり、お母様との共有にしたりする代わりに、お母様には無償で住み続けられる権利(使用貸借権)を設定する。
- 代償分割:
- 特定のお子様(例えば、家業を継ぐ長男)が不動産などの遺産を多く相続する代わりに、お母様に対して金銭(代償金)を支払う。
重要なのは、感情論だけでなく、法的な権利(法定相続分)を意識した上で、具体的な財産の分け方を冷静に話し合うことです。
円満相続のため、二次相続まで見据えた判断を
一次相続において、お父様の遺産をお母様が全て相続するという選択は、一見するとお母様への配慮に満ち、手続きも簡単に見えるかもしれません。
しかし、その裏には、二次相続における以下のようなリスクが潜んでいます。
- お母様による財産の自由な処分(使い込み、贈与)
- 遺言による相続分の変動
- 再婚による相続人の変化
- 判断能力低下による財産管理の問題
- 二次相続での相続税負担の増加
これらのリスクは、当初「円満」に進むはずだった相続を、将来、深刻な家族間の紛争へと発展させかねません。
こうした事態を避けるためには、一次相続の段階で、感情的な配慮だけでなく、法的な権利(法定相続分)も踏まえ、お子様たちもご自身の相続分を確保することが重要です。
もちろん、ご家族ごとの事情は様々です。
二次相続まで見据えた最適な遺産分割の方法は、画一的なものではなく、個別の状況に応じて慎重に検討する必要があります。
ご家族の未来のためにも、目先の「円満」だけでなく、長期的な視点に立った賢明なご判断をされることを願っております。

