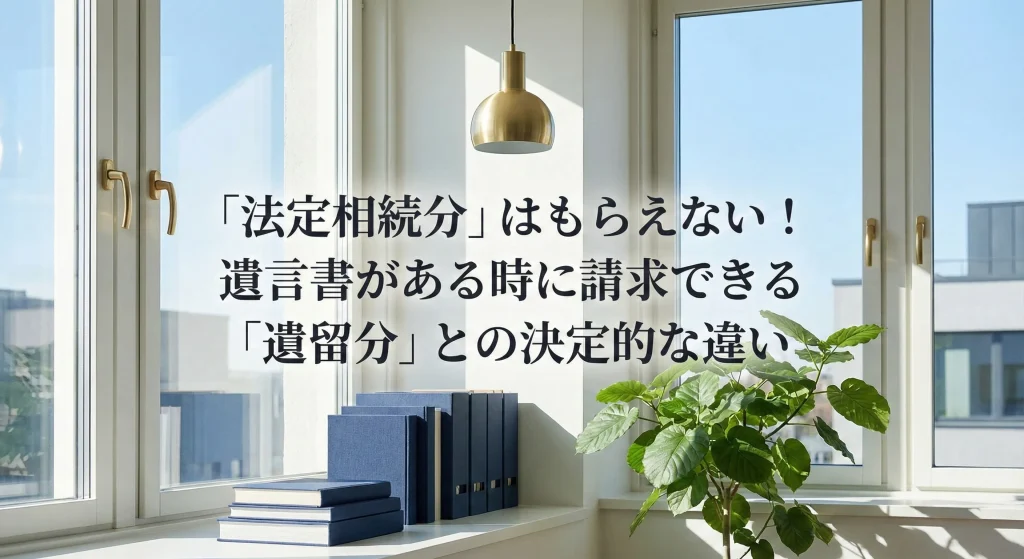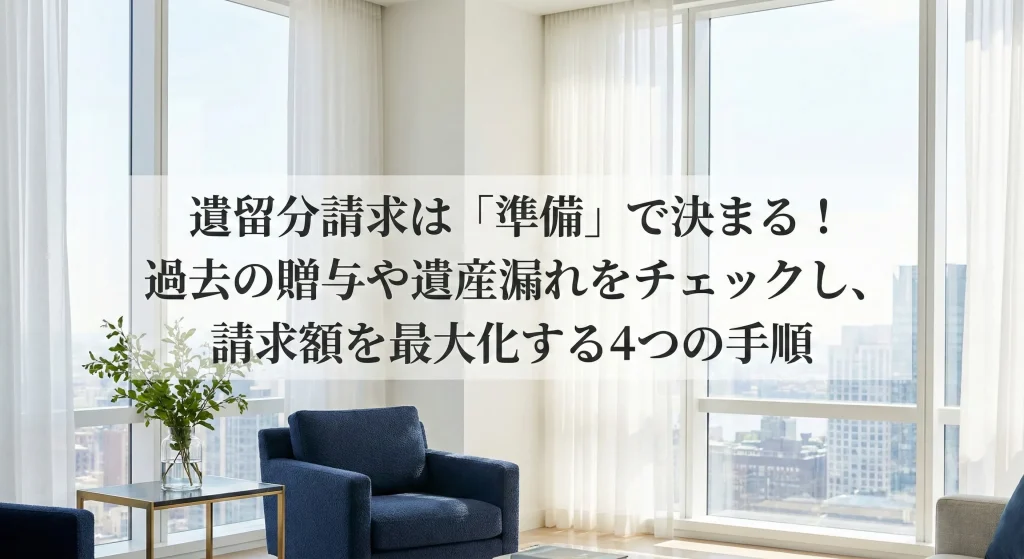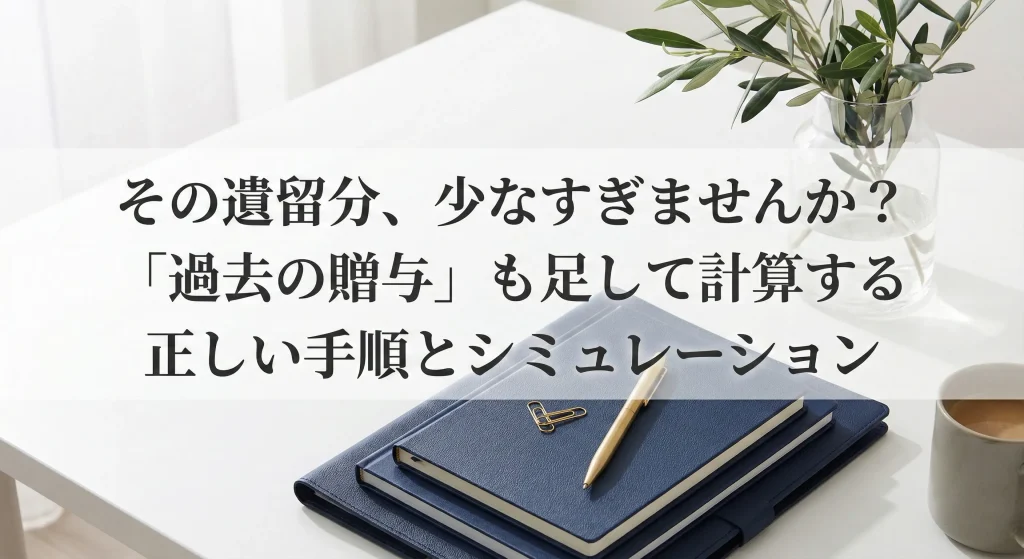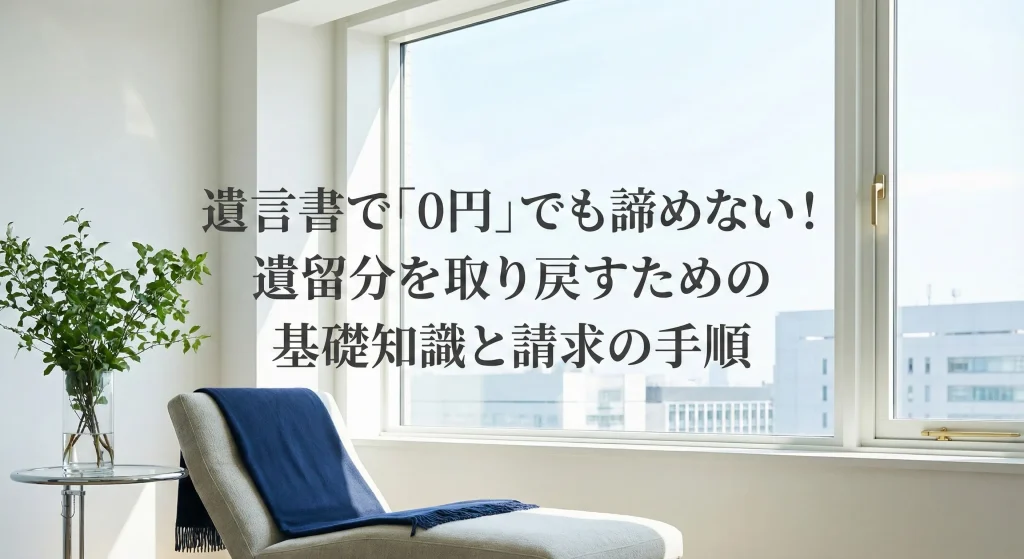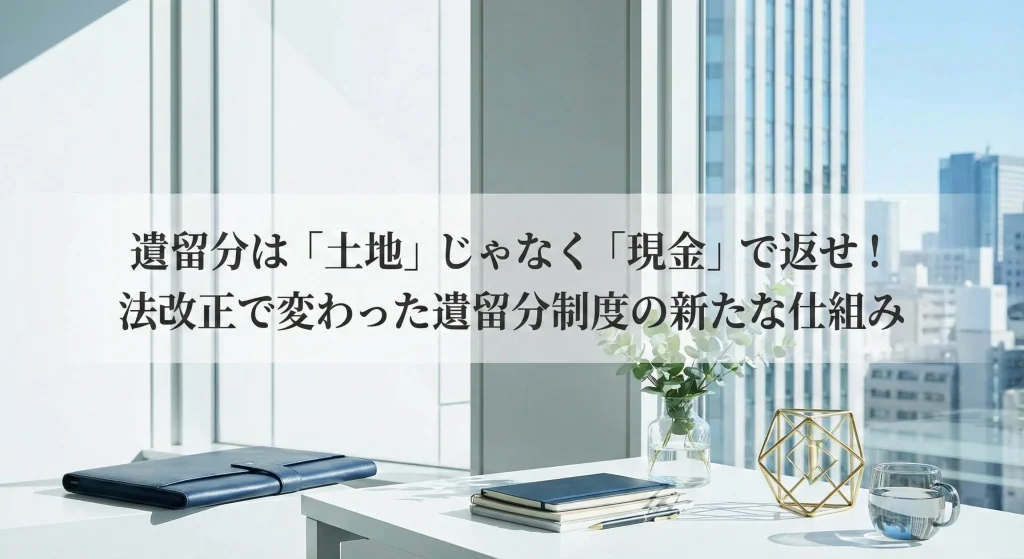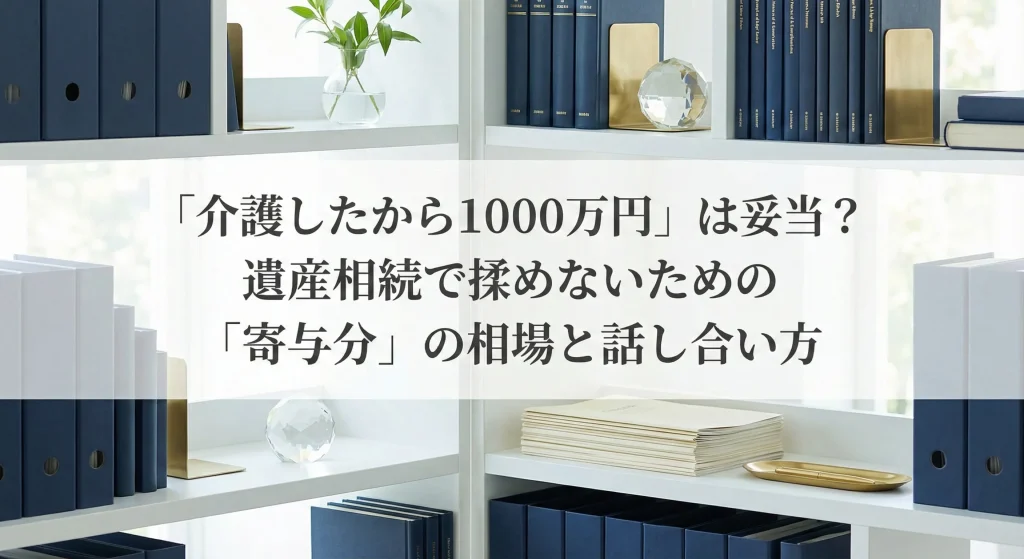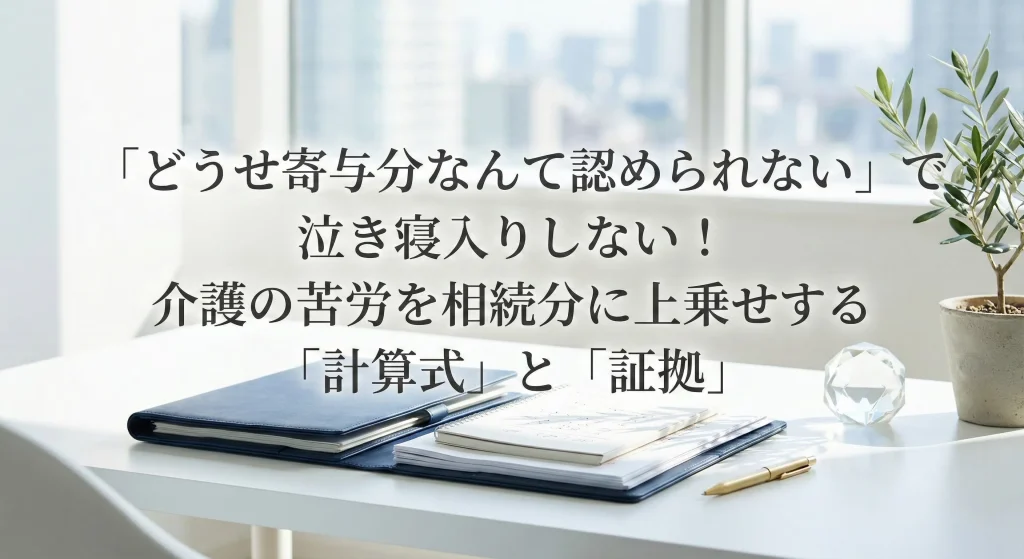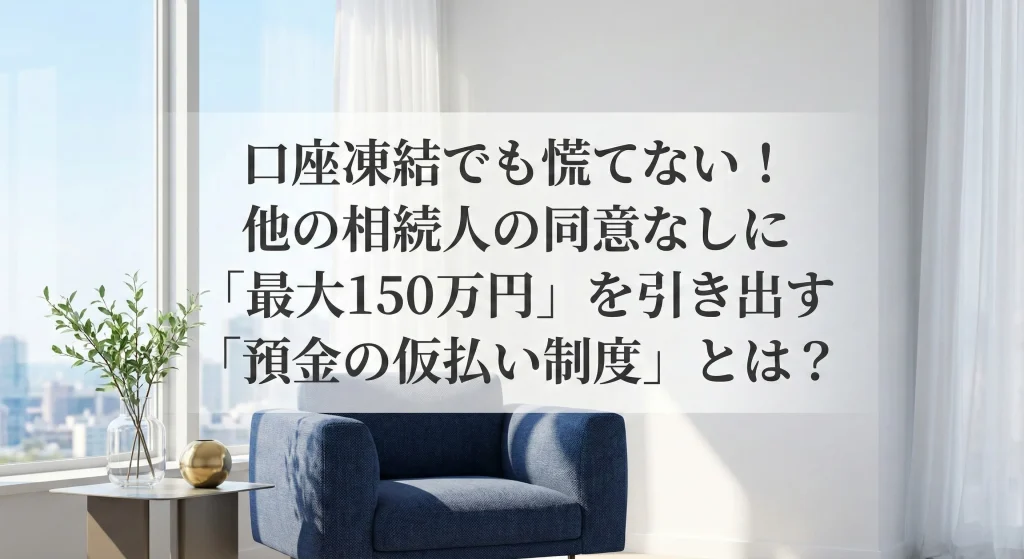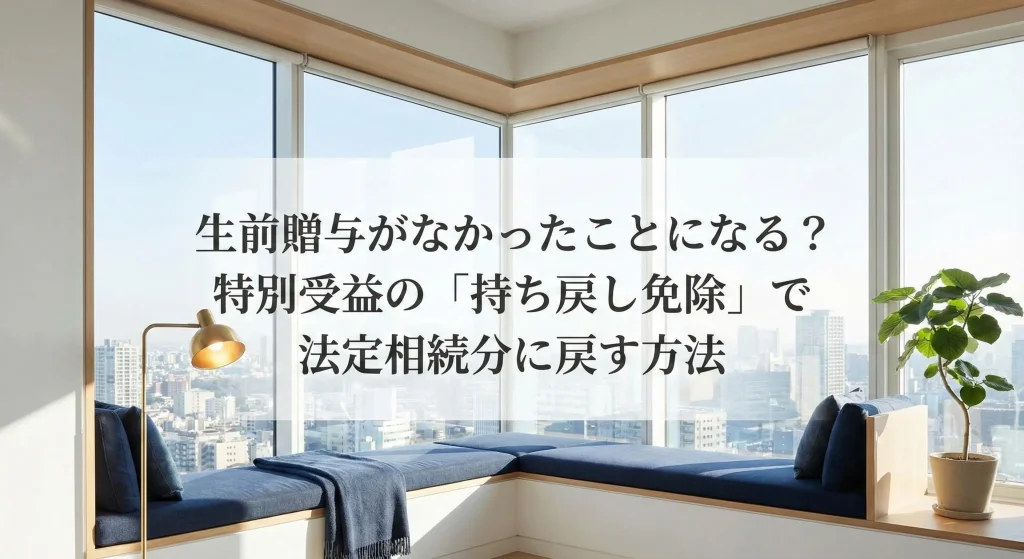相続問題の解決法– 弁護士コラム –
-

「法定相続分」はもらえない!遺言書がある時に請求できる「遺留分」との決定的な違い
「長男に全財産を譲る」 親が亡くなり、そんな不公平な遺言書が出てきたとき、多くの人がこう思います。 「法律では兄弟平等のはずだ。だから自分にも法定相続分(遺産の2分の1)をもらう権利がある!」 残念ですが、その考えは大間違いです。 もしあなた... -

遺留分請求は「準備」で決まる!過去の贈与や遺産漏れをチェックし、請求額を最大化する4つの手順
「遺言書を見たら、兄にすべての財産を譲ると書いてあった」「私の取り分がゼロなんて納得できない」 そう感じて、すぐに「遺留分を払え!」と相手に詰め寄ろうとしていませんか? 少し待ってください。その行動は、あなたにとって大きな損になる可能性が... -

その遺留分、少なすぎませんか?「過去の贈与」も足して計算する正しい手順とシミュレーション
「遺言書を見たら、自分の取り分がゼロだった」「銀行預金の残高が思ったより少ない。この金額の半分しか請求できないの?」 もしあなたが「亡くなった時の通帳残高 × 1/2」が自分の遺留分だと思っているなら、数百万円単位で損をしている可能性があります... -

遺言書で「0円」でも諦めない!遺留分を取り戻すための基礎知識と請求の手順
「全財産を長男に相続させる」「お前には一銭も渡さない」 もし、亡くなった親や配偶者の遺言書にそんな言葉が書かれていたら、目の前が真っ暗になるかもしれません。「自分には何ももらう権利がないのか?」と不安になり、泣き寝入りを考える人もいるでし... -

遺留分は「土地」じゃなく「現金」で返せ!法改正で変わった遺留分制度の新たな仕組み
「実家の不動産やすべての遺産を、長男に相続させる」 親が亡くなり、遺言書を開けてみたらこんな内容だった……。 納得がいかず「遺留分(最低限の取り分)」を請求したいけれど、「兄と実家を共有名義にするのは絶対に嫌だ」「使い道のない土地の持分をも... -

「介護したから1000万円」は妥当?遺産相続で揉めないための「寄与分」の相場と話し合い方
親の介護を一手に引き受けてくれたきょうだいに対し、「感謝」と「負い目」を感じている方は少なくありません。しかし、いざ遺産分割の話になったとき、「お前は何もしていないから相続放棄してほしい」「苦労した分として1000万円上乗せしてほしい」と言... -

「どうせ寄与分なんて認められない」で泣き寝入りしない!介護の苦労を相続分に上乗せする「計算式」と「証拠」
「兄さんは実家に寄り付きもしなかったのに、遺産はきっちり半分なんて納得できない」「仕事を辞めてまで母の介護をした私の苦労は、タダ働きなの?」 あなたは今、そんなやり場のない怒りを抱えていませんか? 何もしなかった兄弟が得をして、一番苦労し... -

口座凍結でも慌てない!他の相続人の同意なしに「最大150万円」を引き出す「預金の仮払い制度」とは?
「葬儀代が払えない…」「親の口座から生活費を出していたのに…」 親の口座が凍結されると、これらのお金はすべてストップしてしまいます。これまでは、どんなに緊急でも「相続人全員の実印と印鑑証明」がなければ解約・払い戻しができませんでした。 しか... -

生前贈与がなかったことになる?特別受益の「持ち戻し免除」で法定相続分に戻す方法
被相続人から生前贈与をもらっていた場合、他の相続人から特別受益の持ち戻しを主張されることがあります。たしかに、原則としては、生前贈与は特別受益になり、遺産分割における相続分は減ります。しかし、「特別受益の持ち戻し免除の意思表示」があれば...